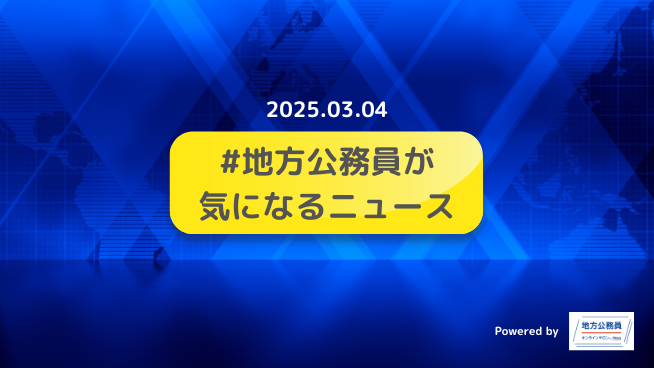記事タイトル:区立小中学校の給食の全野菜をオーガニックに 東京・品川区
https://www.asahi.com/articles/AST2402Q5T24OXIE021M.html
(文=牧野 浩樹)
オーガニック給食をどう考えるか
品川区が給食の全野菜をオーガニックにという施策を実施されるようで、これに対してSNS上で賛否が挙がっているようです。
有機やオーガニックは農業界隈でもバチバチしがちなセンシティブな話題です。扱うのはとても緊張しますが、今回は、有機給食を導入する際の私の考える論点と考えをお伝えしたいと思います。
【1】目的をどう捉えるか
ここに尽きると思います。
そもそも、なぜ有機農産物を導入するのでしょうか?使われがちな言葉としては「安全」「安心」「美味しい」「環境にやさしい(持続可能)」などがあるかと思います。ここが大きな議論を巻き起こします。
「安全」なのか?農業に関わる身からすれば、有機だから「安全」は誤りだと思っています。明確な科学的根拠はありませんし、何よりそもそも的確に農薬を使っているあらゆる農産物も安全だからです。両方とも100点なので、そこに優劣はないと考えます。
「安心」なのか?人の主観なので人それぞれだと思います。
「美味しい」のか?これも科学的根拠は示されていません。そもそも農薬以外に、土壌、気候、鮮度、旬、品種など様々な要因が関わるので、有機だけで判断はできません。
「環境にやさしい(持続可能)」のか?これは難しいですが、持続可能というのはありだと考えます。確かに海外原産の化石燃料を投下して作られる化学肥料や農薬を使用しないという点では持続可能ですし環境にやさしいと思います。
一方で、農業現場にはビニールやマルチなどの様々な資材が使われていて、仮に有機農業をすることでそれらの使用量が増えるのなら本末転倒になります。
これらをまとめると、目的として「より安全」や「安心」、「美味しい」などを使用すると、農業界からすれば「おいおい」となります。農水省の「みどりの食料システム戦略」に使われているような「持続可能な社会にしていくため」というような表現が適任だと思います。
【2】コストをどうするのか
まだまだ有機農産物の面積は少なく(全体の0.7%)、つまり生産量は少ないです。となると他の農産物よりもコストが高くなりがちです。
1企業が食堂を有機にするのは個々の判断ですが、行政が実行するとなると、「そのコスト上昇は必要なのか」「そもそもそんなこと求めていない」という議論が出てきます。
ただ一方で、国として「みどりの食料システム戦略」で有機農業の面積拡大を目指しており、その需要先が増えることは施策を進める上でも大切です。
いろいろと議論の巻き起こる“有機農産物”。皆さんはどう考えますか?
本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。