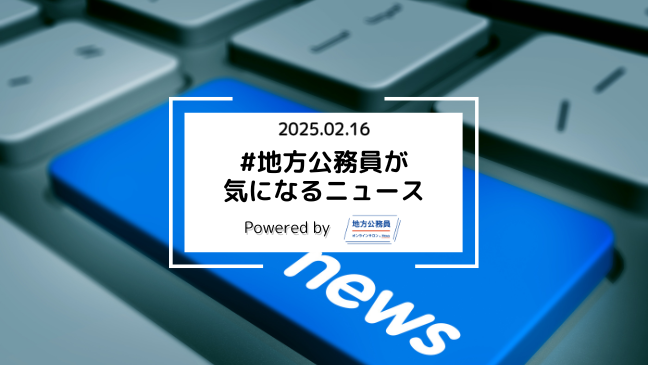記事タイトル:中学校の部活動の地域移行 指導者600人必要も…登録は230人ほど 長野、松本など都市部に偏る 教育長が協力呼びかけ
https://news.yahoo.co.jp/articles/6386ec2eb2d0a937f0dabea598663eb483f54d9b
(文=金澤 剛史)
何度か取り上げている部活動の地域移行です。
長野県教育委員会が中学校の部活動の地域移行にむけ、指導者のリスト化を進めているものの、登録者数は230人ほどと目標値の30%程度に留まっているとのこと。各地で、こうした活動が見られるようになってきました。
駅ビラ配布の効果についてはともかくとして、そもそも指導者の数を集めることがこの問題の解決に当たるのかを考えてみたいと思います。
部活動の地域移行は何を目指す?
『少子化が進展している現実を踏まえ、中学生年代における持続可能なスポーツ・文化活動の環境を身近な地域で整えること』
つまりは「子どもたちが少なくなってきたから、今の時代に応じてどう環境をアップデートさせていくかを考えよう。」
これが目指すべき方向性です。
部活動地域移行はその手段の一つに過ぎず、これだけ見るとシンプルなようにも思えます。それではなぜこの問題がここまで難航するのか(全国的に見ても成功例と言われるケースが聞こえてこないのか)を考えてみました。
①目的は「教員の働き方解決」?
これは報道の仕方にも大いに原因があります。『教員の働き方改革』とセットで報道されていることから、このように捉えられている感がありますし、現場でもこう感じている方が一定数いるのも確かです。
これの何が問題かというと、目的が「教員の負担減」になってしまっている事。その為の手段として、「教員ではなく外部に任せよう」→「受けてくれる人を探そう」という考えになってしまっている事が挙げられます。
つまり、目的及び手段が、本来のものとズレていってしまっていることがこの問題をややこしくしています。そもそも、『地域における担い手不足』は自明の理。少子高齢化の世の中、当然のことながら現役世代も減少しています。
そこで、時間に融通がつくだろうと、手っ取り早く自営業者や退職者の指導者のリストアップが目的化しており、その為の条件面(報酬や諸条件)の議論に終始してしまっています。
しかし、目的を子どもたちのためとするのであれば、まず考えるべきは、例えば『部活動を続けたくとも続けられない子供たちにとって必要な環境を整えていく』といった問いから始めるとやりやすいです。
その解決策の一つとして、スポーツクラブとの連携やスポ少などの受け皿探しなどを検討していく。そこから発生する保護者や当事者の負担についても解決策を考えていくといった具合です。地域移行=教員の代役を探すことではなく、よりよい環境を共に築いてくれる人や組織を探すことにシフトしていくべきです。
本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。