[記事提供=リディラバジャーナル]
「行政がイベント屋になってしまっている」――。
こう語るのは、新潟県十日町市役所・観光交流課の玉城健太さん。以前、産業政策を担当していた玉城さんは市の観光政策についてこう話を続ける。
「十日町市の観光はイベント偏重型になっていました。イベントの実施に追われていて、何のために観光をやっているのかということを考えられていなかった。行政の仕事は直接的に売上を立てることができません。その中で、いかに地域の事業者の売上や雇用の創出につなげられるのかを見据えた、『政策』としての観光をやっていかなければと思っていました」
政策としての観光を考えるために何が必要なのか。玉城さんは、「思いつきで施策を考えるのではなく、なぜそれをやるのかを考えていかなければならないですよね。数字やデータを用いた現状分析をした上で、必要なことを考える習慣をつくっていきたいと考えています」と話す。
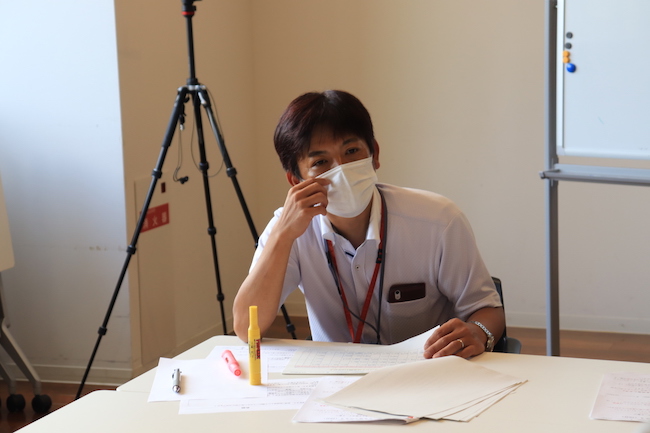
玉城健太さん
大地の芸術祭、十日町雪まつり、松之山温泉、縄文文化などの観光資源を有する新潟県十日町市。2000年度からは、3年に1度開催される現代アート展「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」などにより、訪日外国人も含めて観光客数は増加傾向にある。
一方で、十日町市内で開催されるイベントは年間118件を超え、「イベント疲れ」などが問題視されはじめている。
今回はそんな十日町市の観光を考えるにあたって実施した、政策立案ワークショップの取り組みを紹介する。
データにもとづいて政策立案をおこなう「EBPM(Evidence Based Policy Making)」の考え方をどのように地方創生に活かしていくのか、考えるヒントになれば幸いだ。
※本記事はリディラバが内閣府からの委託事業の一環で制作しております。
アンケートだけでは偏りが生じてしまう可能性も
今回の取り組みでは、株式会社リディラバが内閣府からの委託を受け、十日町市役所の職員および民間事業者を対象に、地域経済分析システム(RESAS:リーサス)を活用した政策立案ワークショップを実施した。
を活用した政策立案ワークショップを実施した.png)
本事業を実施することになった背景について、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局ビッグデータチーム参事官補佐の宇野雄哉さんは次のように話す。
「データ活用と言うと、たとえば、各自治体がホームページで住民を対象にしたアンケートを行っているのですが、それを見ても回答する人は多くないですし、サンプルが偏ってしまう。高齢者ばかりで若い人が答えてくれないなどの課題も聞いています。また、住民宛にアンケートを郵送するとなるとお金がかかります。そうしたコストをかける前に、まずはRESASを使って、データを見てみてほしい。一方で、自治体からは、データをどのように分析して活かせばいいのかわからないという声も聞いているので、そこをハンズオンで支援するワークショップを実施することとしました」
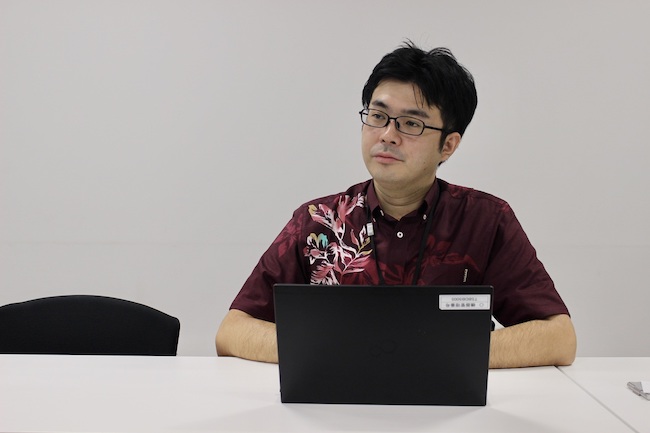
宇野雄哉さん
宇野さんは、「RESASを使って課題を発見するという活用方法もありますし、こんなことが課題になっているのではないかという仮説を検証するためにも活用できると思っています」と強調する。
すでに持っている情報をどう活かすか
初回のワークショップでは、RESASをはじめ、観光政策を考える上で活用できそうなデータのラインナップを検討して、データ収集と分析をおこなった。
リディラバより、RESASを用いて人口推移や産業構造のデータ等を例示したところ、「地区ごとの高齢化率」や「宿泊業の事業所数」、「十日町市内の年間のイベント数」といったデータを活用できるのではないかという意見が市役所職員より挙げられた。
第二回のワークショップからは、自治体職員だけではなく、実際に観光産業を担う民間事業者等も参加。初回で集めたデータをもとに十日町市の現状分析および課題の特定、解決策の検討をおこなった。

現状分析にあたって、観光協会が有していたイベント情報を一覧化したところ、市内のイベント数の多さが論点となった。そこでイベントだけではなく、自然景観や施設など各地域が有する観光資源を、年間の観光入込客数が多い順に整理した。
令和元年度観光入込客数調査をもとに作成。.jpg)
(十日町市役所)令和元年度観光入込客数調査をもとに作成。
これらのデータからは、「隣町で同じようなイベントをやっていたので、連携できるのではないか」「イベントをあまり実施していないものの観光客が来ているエリアもあるので、必ずしもイベントをやる必要はないのではないか」といった意見が出てきた。
宿泊者数は観光客数のうちの10%ほどに留まるといったデータを踏まえて、「夜にイベントを開催したほうがいいのでは」という声もあった。
令和元年度観光入込客数調査をもとに作成。1.jpg)
(十日町市役所)令和元年度観光入込客数調査をもとに作成。
十日町市役所観光交流課の宮澤友和さんは、「これらの観光入込客数などのデータは以前からとっていましたが、数字をとるだけになっていました。それを地域や施設などの区分ごとに加工したり、組み合わせたりして分析することはやっていなかったのですが、それはもったいないことだと気づきました」と振り返る。
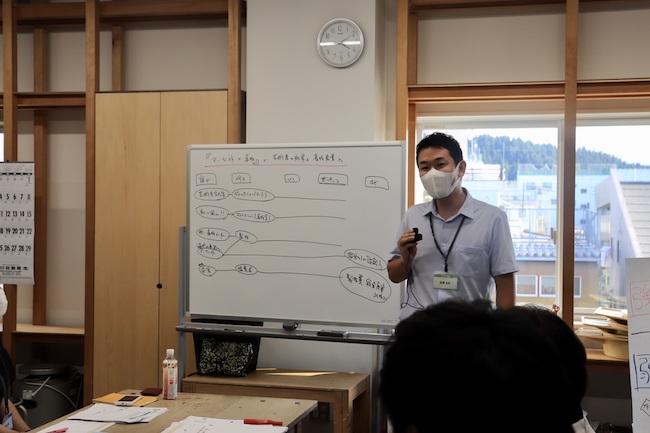
宮澤友和さん
ワークショップでは観光案内所が記録していた問い合わせ内容の分析などもおこなったが、これらはすべて自治体や民間事業者等が情報として持っていたものであり、眠っているデータを掘り起こしてみると、見えてくることがあるとわかった。
「あれもこれも」ではなく、取り組むべきことを「取捨選択する」
第三回のワークショップでは、市役所職員と民間事業者合同のグループをつくり、観光振興に向けた具体的な取り組みと、その実現方法について議論した。
「理想的なイベント・宿泊・交通のあり方」をテーマとしたグループでは、前出のとおり、イベント数が多いわりに、宿泊者数が少ないことが課題として挙げられた。観光客数のうち宿泊者数は10%程度であり、宿泊施設の数も南魚沼市の4分の1ほど。つまり、多くのイベントや観光資源が宿泊に結びついていない。
そこで、観光による経済効果を最大化するためには、宿泊客を増やす、あるいはリピート率を高める施策が必要ではないかという仮説に至った。

RESAS「産業構造マップ」をもとに作成。
また、観光客の滞在時間を延ばすために、一貫したコンセプトにもとづく観光プロモーションの必要性が語られた。
民間事業者からは、「除雪」など住民にとっては日常の出来事も魅力的な体験という宿泊者の声を踏まえて、「非日常の体験」をコンセプトとする提案もあった。
地域の資源を活かしたコンセプトにもとづいて、宿泊・交通などに携わる民間事業者や観光協会、市役所の取り組みを連動させることで、観光客の滞在時間をのばすことができるのではないか。そうした仮説にもとづいて、次のような具体策が提案された。
●市役所が主体となり、地域住民や民間事業者へのヒアリングをおこない、現場の声に立脚したコンセプト立案をおこなう
●複数の観光関連事業者、市役所、観光協会が参加するコンソーシアム形式での情報共有、企画立案をおこなう

このようにRESASをはじめ、さまざまなデータをもとに議論を重ねることで、市役所職員や民間事業者など観光政策を推進するプレイヤーが共通の認識を持ち、取り組むべき課題を見つけることができる。また、課題に対して必要な打ち手を考えるにあたっても、「どこから人が来ているのか」や「いつどこに人が来ているのか」といったデータが活用できる。
もちろん、目の前の職務で手一杯で、データを分析し、議論をおこなう時間が十分にとれないという意見もあるだろう。
しかし、前出の十日町市役所観光交流課・玉城さんは、「今までやってきたことをやりつつ、新しいこともやらなければという発想は捨てたほうがいい」と指摘する。
「確かにデータの分析をして政策立案をしていく過渡期は大変だと思います。ですが政策の検証ができれば、やらなくても良いことが見えてくるはずです。限られた資源の中で何をやらずに、何をやるべきか見極めていくことが必要になってきますよね」
データにもとづく政策立案をおこなうだけではなく、その成果を検証することで、本来やるべき施策に注力していくことが、これからの自治体経営には求められている。
本ワークショップの当日の様子や参加者へのインタビューは、YouTubeにてご覧いただけます!
▼「地方公務員オンラインサロン」のお申し込みはコチラから
https://camp-fire.jp/projects/view/111482
全国で300名以上が参加。自宅参加OK、月に複数回のウェブセミナーを受けられます
▼「HOLGファンクラブ」のお申し込みはコチラから
https://camp-fire.jp/projects/view/111465
・月額500円から、地方公務員や地方自治体を支援することが可能です
※facebookとTwitterでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。
top.jpg)

