『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2025』、5人目の受賞者の紹介です。
※部署名役職名は推薦文登録時時点のものであり、現在とは異なる場合がございます。
木下 義昭(玉名市 建設部 土木課 課長補佐 兼 橋梁メンテナンス係長)
推薦者1:橋本隆(伊勢崎市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
橋梁メンテナンス革命「玉名市モデル」の考案・実践で、橋梁の維持管理費20億円削減!
推薦文
木下さんは、玉名市土木課で橋梁のメンテナンスを担当し、維持管理費20億円削減の偉業を成し遂げました。木下さんによる独自のアイデアは、職員自ら補修を行う「橋梁補修のDIY」。業務の「人材育成」と私生活の「人の群マネ」で数多くの成果を挙げています。
木下さんは、産業機械メーカーから中途採用された技術職です。土木課配属後に担当した業務は、住民の安全を守る橋梁のメンテナンスでした。木下さんが担当した玉名市の橋梁数は800以上に及び、橋梁メンテナンスの進捗は大幅に遅れていました。予算や職員数の減少が進めば、住民の安全を守る役割が果たせなくなるのではないか。この喫緊の課題に対して、迅速な橋梁点検と補修が待ったなしの状況でした。
当時の玉名市は、橋梁点検完了率2%、全職員の技術職率6%、財政力指数0.44という、数字の上では厳しい現実がありました。そこで、木下さんは橋梁補修技術を徹底的に調べ上げ、職員による「橋梁補修のDIY」で業務改善することを考案しました。職員による直営施工を核として、地元建設業との連携、学識経験者との連携による「玉名市モデル」を実践し、予防保全型メンテナンス移行率100%、修繕完了率100%、維持管理費20億円削減を達成したのです。
そんな木下さんは、博士(工学)の資格取得をはじめ、第8回インフラメンテナンス大賞国土交通省「優秀賞」、土木学会インフラメンテナンス賞「優秀論文賞」を受賞しています。また私生活では、「人の群マネ」を目指して「一般社団法人行政エンジニア支援機構(そらゑ)」を設立し、全国の行政エンジニアに向けた講演会開催等による人材育成を行い、全国で苦悩している行政エンジニアに救いの手を差しのべています。
現在、木下さんは業務と私生活を両立して橋梁メンテナンスに尽力されています。日本の将来を見据えて、ひたむきに努力する彼を尊敬し推薦します。
推薦者2:中越 亮太(山口県)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
橋を守るDIY革命でインフラメンテ費を大幅削減し、さらに現場で学ぶ行政エンジニアとしてのスキルアップ
推薦文
玉名市役所の木下義昭さんは、全国の地方自治体が抱える「インフラの老朽化」という難題に対し、「現場から変える」という前例のないアプローチで挑みました。
その名も「玉名市モデル」。それは、財源も人手も足りない中で、「ないならつくる、学ぶ、やってみる!」というDIY精神あふれるインフラメンテナンス改革です。
2016年、熊本地震を経験した木下さんは、「橋は地元で守る時代」だと痛感。当時、玉名市が管理する約830の橋のうち、点検が完了していたのはわずか2%という厳しい状況でした。そこで木下さんは発想を転換し、市職員自らが橋を直して学ぶ「橋梁補修DIY」を導入しました。
市職員が現場で修繕を行いながら知識と技術を習得し、点検記録や工事積算にも関与するOJT体制を構築。さらに、地域建設業者との“分離発注”により地元との連携を深め、大学などとの“学官連携”により技術支援も取り入れました。
その結果、1巡目で要修繕と判定された橋はすべて修繕が完了。2巡目では危険な橋がゼロとなり、従来の外部委託中心の方式と比べて20億円以上のコスト削減も実現しました。
「橋梁補修DIY」に取り組むことで、現場からの多くの気づきが得られ、関わった行政エンジニアのスキルが向上。より質の高いインフラメンテナンスが可能となりました。
このモデルは現在、全国の自治体にノウハウを積極的に発信しており、「橋を守る新たなロールモデル」として注目を集めています。
技術と人材の両面からインフラ維持のあり方を問い直し、「やってみよう!」の精神で新たな道を切り拓いた木下さん。その挑戦と実績は、公務員の可能性と力を全国に示すものであり、公務員アワードにふさわしい功績であると、心から推薦いたします。
推薦者3:宮川 洋一(愛知県)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
地方のインフラメンテナンスの最前線から、まさにこれまでの「社会の常識」を変える技術職員
推薦文
行政エンジニアの立場から、このままでは地方インフラは破綻するとの危機感を感じ、まず自ら考え、行動を起こし、周囲を巻込み、信頼する仲間をつくり、人を育て、自発的に行動する仕組みをつくり、チームで実践した。やり続けるうちに、玉名市は全国どこの自治体も到達したことがない「予防保全型インフラメンテナンス」を確立してしまったのです。それは「玉名モデル」とも呼ばれ、「橋梁DIY」という言葉も生み出しました。瞬く間に日本中に伝播し、全国のインフラメンテナンスを担う市町村、都道府県のみならず、国の技術者までもが実践し始めています。
この傍ら、自らの取組みをもとに九州大学で博士号を取得し、土木学会ではLIMN(ローカルインフラメンテナンスネットワーク)という組織のもと、全国で同じ境遇におかれた仲間の相談を受け、彼らの苦悩を解決する活動を始めました。私はそのころ彼に出会い、行動力、思慮深さ、人間らしさ、洞察力、探求力…、何より懐の広さに度肝を抜かれました。気づけば、彼が設立した社団法人「行政エンジニア支援機構(そらゑ)」に加わり、わが国のインフラメンテナンスを担う行政エンジニアの下支えをすることで、この国の豊かな社会が持続的であり続けるべく活動しています。
機構には、同じ志を持つ全国の技術者仲間が次々賛同しています。これまで培ってきた信頼と人的ネットワークにより、わが国のインフラメンテナンスを持続可能とするための切り札ともいえるインフラの「群マネ」を提唱したわが国のトップクラスの顧問団に直接提言する存在になっています。未来の豊かな社会を支えるインフラを維持し続けるために、まさにこの国の社会の常識を変え、奔走しています。彼自身「すごい」と思っておらず、アワード受賞をすれば「すごい」と分かってもらえるのかもしれません。受賞を機に、機構の取組みを広く知ってもらい、社会を変える後押しをしたいと考えます。
推薦者4:今井 努(周南市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
玉名市モデルの構築による安全安心・行政コスト削減の実現と人の群マネ全国展開による人財ネットワーク構築
推薦文
「現場を知る者こそ、未来を描ける。」
木下さんの仕事ぶりをひとことで言い表すとすれば、そう言えるでしょう。泥臭い現場に根ざした知見と、自ら収集した膨大データに裏打ちされた論理的思考。そして、戦略構築から組織運営までのマネジメント力は極めて希少な存在です。玉名市での取組をまとめた研究成果は「玉名市モデル」として、土木分野の最高峰である公益社団法人土木学会における令和2年の土木学会賞(論文賞)という形で認められ、現在も、組織内外の人財育成に取り組まれている姿を目の当たりにしています。
私は、令和3年に組織外の活動で知り合い、直近では木下さん自らが立ち上げた“一般社団法人行政エンジニア支援機構(通称:そらゑ)”の取組に関わらせていただいています。どの場面においても自らがエンジンとなり、多様な人々の個性・専門性・得意技を的確に見極め、歯車のように組み合わせながら物事を動かす行動力は、機械系の民間技術者経験を経て土木系の公務員技術者に転身した経験からくるものと想像しています。特に“そらゑ”には、立ち上げから1年も経たずに全国から多くの公務員が入会しており、最前線のインフラメンテナンスの現場で苦悩する同志の情報交換・共有・集約の場として国が推進する「地域インフラ群再生戦略マネジメント(通称:群マネ)」のベースとなる「人の群マネ」を具現化しています。彼の行動は、前例のないことへの探究心とスポンジのような吸収力から来ており、新しいことに臆せず飛び込み、誰よりも早くキャッチアップし、実践へ落とし込むスピード感は圧倒的です。これは、自治体の中にとどまらず、地域や分野を越えて学び、成果をシェアし続ける彼の姿勢が育んだものです。
公務員技術者としての実務力と、研究者としての分析力・論理性を兼ね備える彼は、まさに新時代の行政エンジニアであり、全てを高いレベルで実現し続ける木下義昭さんを推薦いたします。
推薦者5:安田 信洋(玉名市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
制約を強みに変える発想の転換:「橋梁補修DIY」「分離発注」!
推薦文
玉名市において、全国の地方自治体が抱える橋梁メンテナンスの課題に、独自の革新的な手法で立ち向かい、顕著な成果を上げてこられました。その取り組みは「玉名市モデル」と呼ばれ、全国の自治体にとって模範となるものです。
木下氏は、地方自治体が抱える「技術力不足」「人員不足」「財源不足」の三重苦を、独自の強みに変えました。限られた予算と人員の中、職員の技術力向上に焦点を当て「橋梁補修DIY」を導入。職員が自ら小規模橋梁を補修することで、実践的な知識・技術を習得し、現場の課題を把握し、必要な対策を見出す力を養いました。人員不足には、地域建設業との協働による「分離発注」を確立。職員のDIY経験に基づく指導で、地域経済活性化と技術底上げを実現。さらに、大学等と連携し高度な技術課題にも対応。この柔軟なアプローチが、玉名市の橋梁メンテナンスを成功に導いた鍵です。
これらの取り組みは「3ステップアプローチ」として体系化され、予防保全型の橋梁メンテナンスへの早期移行を可能にしました。その結果、玉名市では1巡目点検の判定区分Ⅲ・Ⅳに対する修繕完了率100%を達成。2巡目点検では判定区分Ⅲ・Ⅳが0橋となるまでに至りました。これは約20億円以上のコスト削減を達成しただけでなく、職員の技術力向上、地域建設業の活性化、地域全体の安全・安心の向上に繋がる大きな成果です。
木下氏の功績は玉名市にとどまらず、土木学会の活動を通して全国の地方自治体職員の支援にも尽力。2024年には一般社団法人行政エンジニア支援機構を設立し、最前線で働く技術系公務員のネットワーク構築にも取り組んでいます。木下氏の飽くなき探求心と地域への貢献に対する強い思いは、多くの地方公務員の手本です。木下氏の取り組みが全国に広がることで、日本のインフラの未来はより明るいものになると確信し、強く推薦いたします。
推薦者6:伊方 寛睦(玉名市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
地方自治体特有の制約条件の中で、現場発の創意工夫によって橋梁メンテナンスの予防保全型への完全移行
推薦文
「地方公務員が思う本当にすごいと思う地方公務員アワード2025」に、橋梁メンテナンスの改革者である上司の木下義昭さんを推薦いたします。
木下さんが橋梁メンテナンス係に配属された2016年、玉名市は823橋を超える橋梁を抱えながら、点検進捗率わずか2%
という危機的状況でした。財源・人員・技術力不足が深刻で、熊本地震の影響も重なりました。私も大変困惑していました。
この困難な状況で、木下さんはピンチをチャンスに変える「玉名市モデル」を構築されました。これは、市職員が自ら橋梁を補修する「橋梁補修DIY」で現場力を高め、地域建設業者と連携した「分離発注」で措置数を拡大。さらにICT
活用や学識経験者との協働で、技術力不足を補い、作業を効率化しました。この改革の結果は驚くべきものでした。約20億円以上のコスト縮減を達成し、1巡目点検でのⅢ(早期措置段階)・Ⅳ(緊急措置段階)判定橋の修繕完了率100%、そして2巡目点検ではⅢ・Ⅳ判定橋がゼロとなり、完全な予防保全型メンテナンスへの移行を実現しました。
木下さんの真髄は、私たち職員の「やる気」を引き出すOJT
にありました。時には泥まみれになりながらも、現場での経験を通じて、自ら考え行動することの重要性を教えてくださいました。彼のリーダーシップは、私たちの残業時間を減らし、有給休暇取得を増やすという「働き方改革」にも繋がり、職員は「自分たちの橋」への愛着と誇りを持つようになりました。
彼はまさに、地方公務員の模範です。その類まれなる実践力と、制約を工夫の源泉に変える発想力は、この賞にふさわしいと強く推薦いたします。
特別協賛社賞-公職研賞

技術系職員の採用が一層厳しくなる中で、職員の能力向上を軸に、地域や大学との連携など多面的な施策を実施し、メンテナンス品質の飛躍的改善とコスト削減を同時に達成されました。さらに、自組織にとどまらず、全国の行政エンジニアの育成にも力を注がれています。その積極的な姿勢を高く評価した結果、協賛社賞に選定させていただきました。
審査員のコメント
直営化という一見行革に逆行する取組により、委託化による業務の行き過ぎた分散化による非効率、職員の専門性の低下という課題を、「玉名市モデル」を築きあげて解決した手腕と行動力が凄い!(海老澤 功)
橋梁メンテナンスという難題に対し、現場発の創意工夫で全国的にも例のない仕組みを構築。職員育成、地域連携、財政貢献すべてに成果を上げた実践力は圧巻。さらに、全国の行政エンジニア支援にも挑み続ける姿勢が素晴らしいです。(橋本 一磨)
現場を知り尽くし、柔軟な発想で大きな使命感を持って「橋」に向き合っている姿が本当にカッコいい!全国への波及効果が大きい点も凄いです。(小野寺 崇)
私は橋のことは詳しくないのですが、「全国どこの自治体も到達したことがない予防保全型インフラメンテナンス」を確立したことは、素晴らしいことだと感じました(市橋 哲順)
住民の安全を第一に考えて時間を惜しまない姿がかっこいい!技術職が減っている中、実践型技術を身に着けられ、さらに安全も守られる一石二鳥は公務員がやらねばならぬことですね!(中村 広花)
全国的にインフラの老朽化が進んでおり、財政が厳しい自治体が多い中で、玉名市の取組は全国の自治体に光明をもたらす事例だと思います。20億円の経費削減というのも素晴らしいです。(安高 昌輝)
木下 義昭さん、受賞おめでとうございます!
【地方公務員アワード2025 受賞者の推薦文はこちら】
(1)齋藤 久光 (2)和田 真人 (3)鈴木 満明 (4)油谷 百合子
(5)木下 義昭 (6)天野 博之 (7)朝比奈 克至 (8)村田 大地
(9)上田 昌子 (10)沼 泰弘 (11)及川 慎太郎 (12)横井 直人
【ネクストホープ賞(30歳以下)受賞者の推薦文はこちら】
『地方公務員アワード2025』全体発表はコチラ
協賛

NECグループの社会価値創造をICTで実現する中核会社であり、システムの実装に強みがあります。社内のDXにも継続的に取り組み、その経験を活かし、お客様や社会のDX推進に貢献しています。そして、国内トップクラスの10,000人を超えるエンジニアを擁する企業として、社会基盤をICTで支えるとともに、お客様の企業価値向上や社会課題解決に貢献するSI・サービスを全国で提供しています。

「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、企業とメディア、生活者をつなぐインターネットサービス「PR TIMES」を運営し、地方自治体600市区町村を含む10万社超が利用。地域情報を流通させる為の枠組みづくりとして、47都道府県で銀行、メディア、自治体と提携をし、各地域事業者の情報発信を支援しています。(R7年5月時点)

「AlphaDrive Region」では、地域の可能性を信じて、地域の企業や自治体向けに新規事業開発・人材育成・組織活性化などをご支援いたしております。地域ならではの難しい課題解決に日々向き合う方々の仲間として、共に考えながら伴走支援を行なっております。「地域の未来」を一緒に創っていきましょう。
-300x270.png)
自治体と企業の連携を創出する官民連携事業を展開しています。自治体が抱える社会課題解決に向け、両者の間に入り「導き役」として事業の伴走をし、善き前例をともにつくり、持続可能なまちづくりを推進しています。自治体と企業の強みとニーズ、双方の利益を考え、官民連携の計画から実行、伴走までを行います。

自治体業務において、各種実績をもつ元公務員メンバーを中心に、ふるさと納税・シティプロ・広報支援等を実施。課題抽出・戦略立案といったコンサルティング機能だけでなく、業務実施を担う実働部隊も兼ね備え、地域ごとの課題や理想に伴走。会社の詳細はこちら(https://locusbridge.jp/)

公職研は1971年創業の地方自治専門の出版社です。自治体職員や地方自治関連の出版に加え、人材採用や人材育成、試験制度、研修制度など人事に関わる幅広いテーマで、実務に即した支援を通じて自治体の組織力強化をサポートしています。
自治体の採用業務を支援する、募集情報発信サイト「公務comcom」も運営しております。
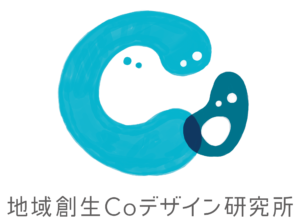
「持続可能な地域を、みんなと一緒に」NTT西日本グループの知見を活かした一気通貫の地域創生コンサルティングにより、「課題探索」から「社会実装」まで伴走する「地域創生」専門の研究所です。まちづくりや観光、GX(グリーントランスフォーメーション)、医療分野などを中心に、地域創生Coデザイン研究所は自治体や企業など地域の主体の皆さまと共に、地域課題の解決をめざしています。
メディア協賛


『自治体通信』は、イシン株式会社が運営する、経営感覚をもって課題解決に取り組む自治体とそれをサポートする民間企業を紹介する情報誌です。全国の都道府県市区町村を中心に合計約30,000部を送付しています。先進自治体の具体的な取り組みをはじめ、自治体経営に役立つ情報をお届けします。

株式会社ジチタイワークスが編集・制作する「ヒントとアイデアを集める行政マガジン」を毎号約11.5万部発行し、WEB版でも限定コンテンツを展開!仕事に活かせる事例を丁寧に取材・紹介し、自治体の課題解決を強力に後押し。また、公私に寄り添う公務員向けセミナーも好評です。

『マイ広報紙』は、毎月1000以上の自治体広報紙を記事ごとにテキストデータ化し公開するプラットフォームです。
自治体毎の情報が1つに詰まった自治体ページや多言語翻訳・音声読み上げ機能、ウェブアクセシビリティ対応など、どなたにも見やすく伝わる広報の実現を目指しています。(運営:スパイラル株式会社)
後援

当センターは活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、地域活性化のための諸活動の支援・地域振興の推進を寄与することを目的に設立し、地域を応援しています。

地域に飛び出す公務員を応援するために、約50人の首長が参加。過去4回にわたって「地域に飛び出す公務員アウォード」を主宰。過去の受賞者プレゼンやサミットの内容はこちら。
![JL-01-Mark-[更新済み]_03](https://www.holg.jp/wp-content/uploads/2019/07/JL-01-Mark-更新済み_03-291x300.png)
Jリーグと全国60のJクラブは地域の人たちをハッピーにしたいと願って、社会連携活動「シャレン!」をおこなってきました。これからもより多くの皆さんと手を取り合って一緒に豊かなまちをつくることに挑戦します。
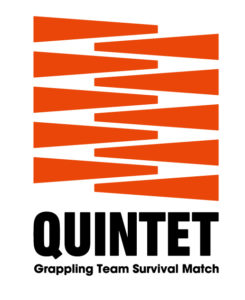
格闘家・桜庭和志が立ち上げた打撃のない安全な組み技競技ブランド。老若男女が取り組める健康増進・防犯対策として、過去に秋田県、生駒市、潟上市と「ねわざ祭」を開催。全国の自治体とも連携を図っています。

Code for Japanは街の課題を市民が主体となってテクノロジーで解決することを目指すシビックテック・コミュニティです。

「社会の無関心を打破する」をミッションに、社会問題に関するスタディツアーを企画運営。地域住民向けにツアー企画スクールを開催し、外部事業者に頼ることのない、持続的な関係人口の創出に貢献しています。詳細はこちら。

マッセOSAKAでは、大阪府内市町村職員に対する研修事業や広域的な行政課題についての調査・研究事業を実施しています。
最新の刊行物、研究成果等詳細についてはこちら。
アンバサダー



