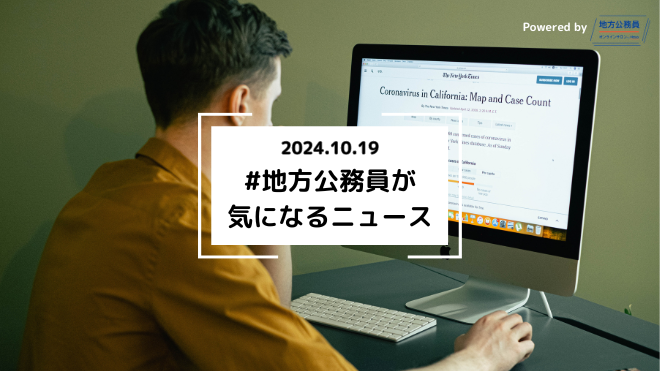記事タイトル:(地方公会計)研究会取りまとめ骨子案について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000967246.pdf
(文=川口 克仁)
私も委員を務めている総務省の地方公会計研究会が、「研究会取りまとめ骨子案」をリリースしたので簡単に紹介しておきます。ちなみにこの話題(取りまとめ骨子案)ですが、「iJAMP」の官庁速報で一瞬だけ上位に上がってすぐに消え、旧Twitterで検索しても話題に上がらず、ネットで検索してもニュースとして取り上げられていないようです。コロナ禍以降、地方公会計の話題性はかなり後退したなぁと実感しました。今後の地方公会計の行方はどうなるのでしょうか。
さて、この研究会のミッションは、「地方公会計情報の一層の活用方法の検討」と、「専門的な視点から統一的な基準の検証・改善」を行うことにあります。第1回は令和4年8月、直近は第10回が令和6年9月に開催されました。
研究会は、地方公会計の理解と活用が進まない現状に危機感を抱いており、その原因と解決策を探ることを強い課題としていました。議事録がネットで公開されてますのでいくつか紹介します。
『活用が進まない原因としては、2つあるのではないか。1つは、自治体の置かれた環境として、時間が限られている、人事異動が頻繁である、作成と活用の部署が異なる、決算情報を基にしている財務書類は予算よりも優先順位が下がるといったこと。もう1つは、会計リテラシーの問題。統一的な基準が難解で、理解に非常に時間を要する。難解だから外部委託をしても、納品物を公表するに留まり、内容を理解する時間がなく、分析も進まないために活用に至らないのではないか。』
『平成 29 年度の研究会において、どのような状態が実現すれば「活用」といえるかについて、一定の課題が解決できたときと定義づけた。だが、当時自治体職員には、そもそも地方公会計を活用するという意識を持っていなかったことや、財務書類の情報を利用するだけでは課題解決に直結せず、議会合意や住民理解という一定のプロセスが必要であること、固定資産台帳や財務書類を作成したことで財政状態が良くなるのではないかといった魔法の杖のような誤解とも言える期待に対して、結果的にそうはならなかったこと等を通して、地方公会計は役に立たないのではないかと思われてしまい、活用に進んでいかなかったのではないか。』
『活用を具体的に要請することで「とにかく一歩目だけやってみてくれないか」というのも一案ではないか。』
などの意見が提出されました。
私が研究会で提案したのは、「部品としての活用」という考え方です。施設別、事業別のセグメント分析はとても手間がかかります。そういう高尚な話ではなく、地方公会計に含まれるデータを手軽な部品として意思決定に活用する手法を説明しました。お気軽すぎて「活用」として認識されてこなかったのを、活用の定義に加えてもいいんじゃないか。自分では当たり前でしたが、事務局的には意外な指摘だったようです。
今後の地方公会計の行方ですが、更に話題性を失っていくのではないかと危惧しています。法令等の根拠もなく、決算統計のような統計としての基準の統一性も弱いために、他団体比較が今後ますます困難になることが予想されます。それではどうすれば良いのか、ごくごく私的な見解を述べたいと思います。
本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。