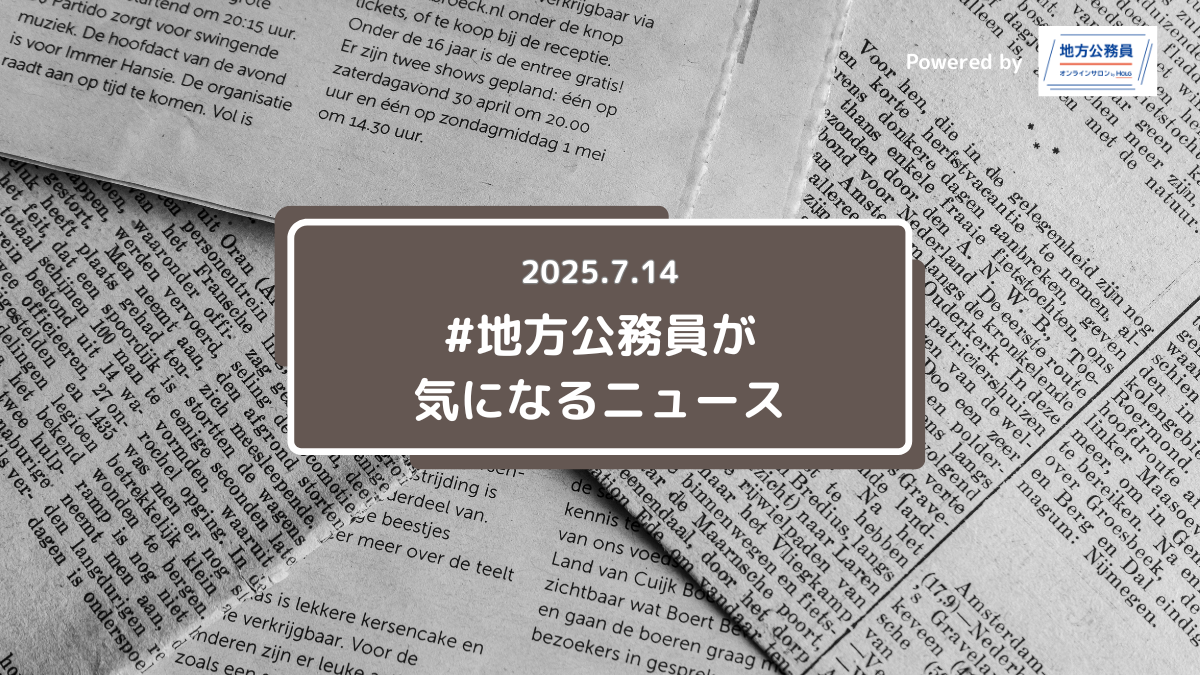記事タイトル:「バス運転手25人欠員…10月からバスを大幅減便」
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb43e0ecd6bc94eb2fd4d0543f182ad6e752b6e0
(文=神山 伸一)
今回取り上げるのは、「地域公共交通の未来」です。
バスの減便や路線の廃止が相次ぐ
地域公共交通が危機に瀕しています。同様のニュースは、全国各地で取り上げられており、多くの自治体職員にとって他人事ではなく、まさに「自分事」として受け止めていると思います。その背景には、労働者の働き方改革とともに、団塊の世代の大量退職による労働力不足、いわゆる「2025年問題」があります。資金不足というよりも労働者不足により交通網の維持が困難になりつつあるというのです。
バス路線を残してほしいという住民の声
住民からは「バスがなくなると生活が不便になる」「高齢者の移動手段が奪われる」といった声が上がっています。公共交通は、住民の身近な移動手段であり、通院や買い物、通学など、日常生活を支える重要なインフラです。その存続を望む声は大きく、自治体としても何とか維持していきたいと強く願っています。
一方で、バス利用者はコロナ禍で激減し、その後も利用者数が回復しない減少傾向にあり、住民の声と実態に乖離があるとも言われています。高齢化が進む中で、移動手段としての公共交通の重要性は増す一方で、利用者の伸び悩み、担い手不足という現実に直面しているのです。
新たな技術の導入
公共交通は地域のライフラインとして欠かせない存在ですが、利用者が少ない路線、いわゆる不採算路線は、事業者の撤退が相次いでいます。 この問題に対し、国は新たな技術の導入を模索しています。オンデマンドバスや自動運転バスの実証実験が各地で始まり、効率的な運行を目指す動きも見られます。しかし、これらの技術はまだ実験段階にあり、維持コストやインフラ整備の課題も残ります。
地域公共交通は、住民の生活の質や地域経済の活性化にも直結する重要なテーマです。技術革新によって新たな可能性が開かれる一方で、地域の実情に即した制度設計と住民の理解が不可欠なのです。
・・・続きはサロン内で。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます