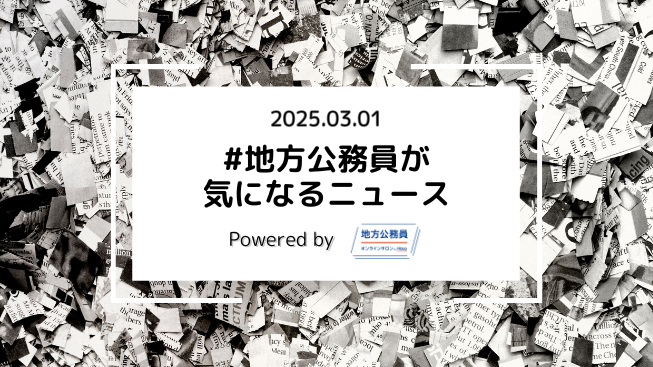記事タイトル:佐賀県が職員を「能力不足」で分限免職 – 「公務員は安泰」は今や昔?
https://mainichi.jp/articles/20250214/k00/00m/010/193000c
(文=鳥羽 稔)
本日は、地方公務員の「身分保障」について取り上げます!
ぜひお読みください!
記事概要
佐賀県は2024年、50代の男性職員2人を「能力不足」を理由に、民間の「解雇」に相当する分限免職処分としました。佐賀県がこの理由で正規職員を分限免職するのは初めてのことです。背景には、各自治体で進む成果主義の導入があると考えられます。これにより、「公務員は安定している」という従来のイメージに変化が生じている可能性があります。
県によると、処分は2024年2月29日付で行われました。職員の問題行動として、以下の点が挙げられています。
- 事務作業で同じミスを繰り返す
- 上司の指示に従わない
- 通常1週間で完了する業務に3か月以上を要し、業務に支障をきたす
これらの問題を受け、県は2022年末から2か月間業務を観察し、2023年4月から半年間、能力向上支援プログラムで指導を実施しました。
しかし、改善が見られなかったため、他県の事例も参考にし、「最下位の職位に降任しても見合った仕事ができる見込みがなく、他の業務でも職務遂行能力の向上が見込めない」と判断し、分限免職の処分を決定しました。
分限処分とは?
分限処分とは、「身“分”保障の“限”度を超えた処分」のことを指します。
地方公務員法では、法律および条例に基づく事由以外で、公務員をその意に反して免職、降任、休職、降給させることはできません(地方公務員法第27条第2項)。また、その事由は以下の4つに分類されています(地方公務員法第28条)。
- 勤務実績不良
- 心身の故障
- 適格性欠如
- 職制の改廃
今回の事例では、職員の勤務実績が著しく悪く、指導プログラムを実施しても改善が見られなかったため、分限免職に至りました。
地方公務員法第28条第1項の「勤務実績がよくない場合」に該当する、つまり「働く能力が極端に低く、このままでは組織運営に支障が生じるレベル」と判断されたわけです。
今日は、分限処分の趣旨・仕組み、判断のポイント、この事案から得られる示唆について、深堀りしたいと思います。
本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。