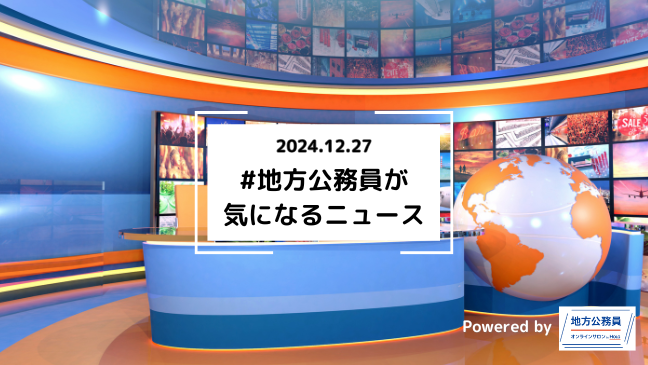記事タイトル:大規模災害時に被災地に教員派遣へ「D−EST」基本方針取りまとめ
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000393701.html
(文=渡邉 雄太)
記事概要
文部科学省は大規模な災害が発生した際、学校の早期再開などを支援する教職員を被災地に派遣する仕組み「D−EST(Disaster Education Support Team)」について、基本方針を取りまとめた。
元日に発生した能登半島地震では、被災地以外の自治体から学習や夜間の生活指導などを行う教職員やスクールカウンセラーが派遣され、学校の早期再開に向けた支援が行われた。
一方、被災地の状況やニーズの把握に時間がかかるなどの課題も明らかになり、的確に教職員らを派遣する仕組み作りに向けた議論が進められてきた。
増える災害派遣制度
災害派遣といえば自衛隊や消防、警察、そしてDMAT(医療)などがイメージされるところと思います。
近年では、これ以外にも、保健、福祉などなど専門分野ごとに制度が新設されています。そこへ今回、教職員についても制度化するというものです。
私見ですが、専門分野ごとに災害派遣の調整・人選が行われることは合理的であると思っています。
制度化の弱点・建前と実際の相違が原因?
担当省庁が明確なものもあれば、複数に渡るものなど様々かと思います。
それだけだとまだいいのですが、建前と実際が異なるものは厄介に感じています。
罹災証明関連ばかり発信して申し訳ないのですが、まさに、この業務がそれです。
被害程度を判定する被害認定調査については、「研修を受ければ誰でもできる簡単な調査」という建前があります。しかしながらこれは、人員が多数必要であるからであって、実際は、一定程度の知見が必要です。(完全に私見ですが…)
派遣を制度化するということは、名簿作成をすることになるのが一般的であるものの、それだと必要数が確保されないのではないかという課題が浮かびます。
実際、応急対策職員派遣制度(総務省)への登録者が南海トラフ想定では数が足りないということで、とにかく登録者を増やすという流れになっています。
また、被害認定調査については、類似業務が固定資産税部門(総務省自治税務局)ですが、所管は内閣府、現行の職員派遣は総務省自治行政局公務員部(一般職員の短期派遣)であるなど、ぐちゃぐちゃな印象です。派遣制度を作るとしたらどこなのか…こういう業務は他にもいろいろあるはずです。
一般職員の派遣では対応が難しいことからうまくいっていない、歯がゆさが残ることも多いと思います。
では、何か良案はないのか、自分なりに考えてみました。
ほかにもあれば教えてください!
本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。