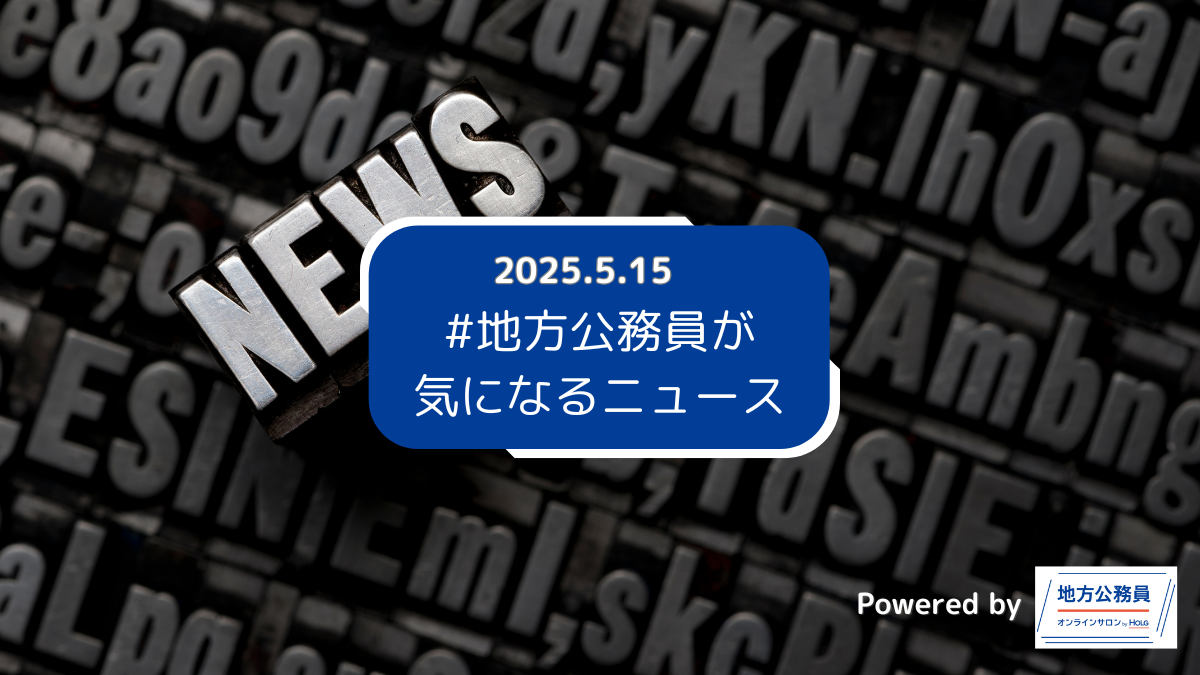記事タイトル:就職活動の日程遵守や配慮要請…文科省が周知
https://reseed.resemom.jp/article/2025/05/08/10836.html
(文=鵜飼洋一郎)
公務員試験業界では、4月下旬に東京都特別区の一次試験、昨日の5月10日に裁判所事務官の一次試験が終わり、と、大型イベントがひとつずつ消化されつつあります。一次試験が終わると、受験者の方々は二次試験の対策に本格的に入ります。しっかりと志望する省庁や自治体の研究をしていただいて、ご自身の良い人生のために、入社後のキャリア構築につなげていって頂きたいなと思います。
さて、そんな時期ですが相変わらず公務員試験関係ではこれといったニュースはありません。今回は、いつもよりさらにニッチに、就職活動の時期に関する仕組みついてのニュースを取り上げました(誰得)。
記事では、「就職問題懇談会」という大学関係団体の代表者が集まった会議からの提言を、文部科学省がWebサイトに掲載した、というものです。
この「就職問題懇談会」ですが、かつての「就職協定」が世に生まれた1953年に、同じ名前の懇談会が存在していました。当時はメンバーに関係省庁の職員も入っていたようで、今の懇談会との連続性がどの程度あるかは分かりませんが、おそらくは伝統ある懇談会なのかなと思います。
申し合わせの中で、就職・採用活動日程ルールについて、次の日程を原則とするよう掲げています。
広報活動開始
「卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降」
採用選考活動開始
「卒業・修了年度の6月1日以降」
正式な内定日
「卒業・修了年度の10月1日以降」
うーん、昨今の「生き馬の目を抜く」ような採用動向を見ると、これは実現不可能なのではと思ってしまいます。
就職協定は1953年に初めて生まれ、その後内容やメンバーについても変化があったものの、最終的には1997年に廃止されました。当初から問題にしていたのは、企業がものすごく早い時期から学生を囲い込んでしまう「青田買い」が、大学の学習・研究に悪影響を及ぼすという点です。
とはいえ、採用する側も必死、就活する側も必死です。その中で、ある意味、当事者から一歩、距離のある大学サイドがどうルールを語るかは、なかなか難しい問題ですね。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。