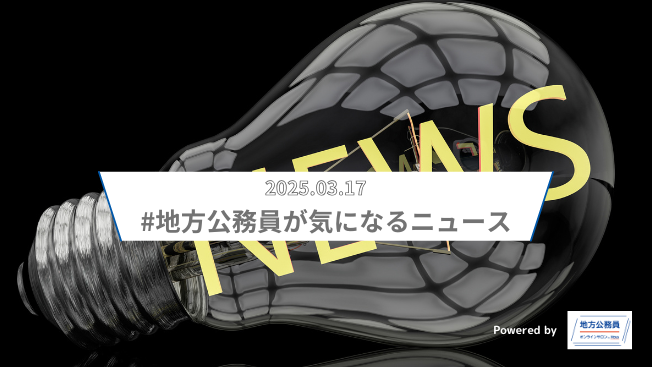記事タイトル:国民健康保険の保険料上限 来年度から3万円引き上げ92万円に
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624941000.html
(文=清原 茂史)
今回は、国民健康保険料の決まり方についてお話ししましょう。取り上げたのは少し前の記事ですが、目下、どの自治体でも「高い国保料はなんとかならないのか」といった話題が3月(2月)議会で上がっているところかと思います。
まず、国保料そのものについて、概観しておきます。国保料は以下の要素から構成されます(各市町村の判断により、これらのうち2~4つが課されます)。
- 応益割・均等割…世帯に属する被保険者数に応じて賦課
- 応益割・平等割…世帯ごとに賦課
- 応能割・所得割…世帯に属する被保険者の所得に応じて賦課
- 応能割・資産割…世帯に属する被保険者の固定資産税額に応じて賦課
なお、低所得者については軽減制度があり、応益割の一定割合(7・5・2割)が減額されます。
また、高所得者については、あまりに高額な保険料を課すると納付意欲に影響するといった理由から、賦課限度額(上限額)が設けられます。今回の記事は、この限度額が引き上げられるという内容です。
そしてあまり知られていないのが、保険料率がどう決まるかについてです。
平成30年度の国保広域化
前回、日本の公的医療保険制度は社会保険方式をとっていることをお伝えしました。要は、保険加入者(被保険者)で拠出された保険料を財源として保険給付を行うというものでした。そうすると、特に小規模な保険者(市町村)で高額な医療費が発生した場合に、保険料が大きく変動して財政運営が不安定になるという問題があります。
これを受けて、平成30年度に「国保広域化」という国保制度改革が行われ、都道府県が財政運営の責任主体となりました。具体的には、都道府県が市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定して都道府県全体の保険給付にかかる財源を一元的に集めた上で、保険給付に必要な費用全額を市町村に対して支払う形となりました。一方、市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金に見合った保険料を設定、徴収して都道府県に納付することとなります。こうすることで、市町村単位で運営するよりも国保料の乱高下が抑えられるというわけです。
一般会計との考え方の違い
国民健康保険は、市町村(および都道府県)において特別会計を設置しなければならないとされていますが、今述べたことから、国保特会と一般会計とで財政運営の考え方が決定的に異なってくることにお気づきなりましたでしょうか。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます。