『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2025』、12人目の受賞者の紹介です。
※部署名役職名は推薦文登録時時点のものであり、現在とは異なる場合がございます。
横井 直人(鯖江市 都市計画課 課長補佐)
推薦者1:酒井 ゆきこ(鯖江市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
0→1を達成する市民の影の立役者
推薦文
市民主役のまち鯖江で、10年以上前から市の職員の枠を超え、市民の新しい挑戦の影の立役者と言ってもいいのが横井氏。
「大丈夫だよ!やってみたら?」
新しい挑戦へのハードルを低くしてくれる一言は、本当に心強いものです。
そして人と人を繋げて挑戦を成功へと導いてくれました。
私がハンドメイド作家として活動していた頃、鯖江ではハンドメイドのイベントが一つしかありませんでした。それがまさに横井氏が企画・運営していた『CAVASABA〜さばえクラフトマーケット〜』。私はその出展者として参加させていただいたのですが、「他にも鯖江市でのハンドメイドイベントを増やしたい」と相談したところ、イベント開催のためのノウハウを余す事なく教えてくださいました。それに加え、鯖江市の若手職員を巻き込んだ”まちづくりサポーター制度(まちサポ)”を教えていただき、もっとも課題だった当日の人員不足も解消できました。それが、今や年に一度開催の、マルSABAへとつながっています(2025年までに11回の開催)。子どもから大人まで約2000人が来場する鯖江市での恒例イベントへと成長しました。
その他にも、仲間と一緒におこなった、子ども食堂「ゆるい食堂」の開催にあたって、鯖江市内の食材提供者を繋げていただいたこともありました。
困ったことを相談をしたら、必ず何か解決策を提案してくれるのが横井氏です。
鯖江市民の「やってみたい!」を、ご自分の経験を踏まえながらサポートすることで、私たち市民の活躍が、その後のまちづくりへと生かされています。
自分が前に出るのではなく、市民の活躍をバックアップする影の立役者に徹する横井氏は「本当にすごい!!!」と思います。よって地方公務員アワードに推薦します。
推薦者2:荒木 芽紅美(鯖江市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
雑談から始まったアイデアが、北陸最大級のイベントに!
柳のような男が市役所に新しい風を吹かせる
推薦文
市役所って、どうしても「前例がない」「規定にない」っていう“お役所ワード”が立ちはだかる。まるで鉄壁のガード。どちらかと言えば私も壁をつくる方でした。
でも、そんな空気をスッと変えてしまうのが横井くん。柔らかいけど芯があって、問題が起きても慌てず騒がず、冷静に、そして前向きに対応してくれる。風が吹いても、しなやかに受け流すまさに“柳のような男”私はいつもそう呼んでいます。
ある日、何気ない雑談の中で「めがねのまちさばえ」で何か面白いことできないかな〜って話してたら、「ものづくりマーケットやってみたいね!」って盛り上がり、最初は私も完全にノリで話をしていただけでした。でも、横井くんの行動力と巻き込み力がすごすぎて、気づいたら地域のママさんたちと実行委員会までできて、「え、もうチラシ作ってるの!?」っていうスピード感です。
彼は市役所の枠を軽々と飛び越えて、地域の人たちと自然につながっていくんです。裏方でも表でも、いつも全力。しかも楽しそうにやるから、周りの人も「え、なんか面白そう!」ってどんどん集まってくる。結果、今では北陸最大級のものづくりイベントにまで成長。あの雑談から始まったとは思えない規模感です。
市民の声には「うんうん、わかる!」って共感し、課題には「よし、やってみよう!」と即対応。柔軟だけどブレないその姿勢に、私も何度も助けられてきました。市役所の中で、こんなふうに新しい風を吹かせてくれる人って本当に貴重。これからも、横井くんみたいな“風通しのいい人”が地域を動かしていくんだろうなって、心から思っています。
推薦者3:太田 弘純(鯖江市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
人を巻き込み、まちを本気で動かすプロデュース力!
推薦文
地方自治体のプロモーションといえば、外注頼みの一過性のキャンペーンになりがちですが、横井さんは違いました。「自らが自分たちのまちを誇れるようにすること」こそが本当のブランディングだと信じ、「誰と、どうつくるか」にこだわり、市民や若者、企業、関係人口を巻き込んでゼロから仕組みを築いてきました。
総合政策課という部署でご一緒させていただいた横井さんのすごさは、「おもしろそう」と感じた瞬間に動く嗅覚と、人を自然と巻き込んでいく力にあります。思いつきを行動に移し、地元の人や企業、クリエイターまでを当事者として引き込んでしまう。その象徴が、まちのブランド戦略「つくる、さばえ」や「SDGsフェス」の成功です。
「つくる、さばえ」では、まちの魅力を多様なステークホルダーとともに言語化・可視化し、“鯖江らしさ”を内側から育てました。材料しかなかった状態から、実効性のある提言にまで導けたのは、横井さんの対話力と関係性の深さがあったからこそ。さらに「さばえまつり」の立ち上げや、政策にデザイン思考を取り入れるきっかけにもなりました。
また、SDGsフェスでは、陸上競技場という大きな舞台で多様な出展とステージ企画を成功させ、まちの新たな顔をつくりました。ほかにも観光・グルメの魅力を発信する公式インスタ「さばえる」の立ち上げにも関わり、多角的なプロモーションを展開しています。
全国に知られる「鯖江市役所JK課」も、実は横井さんが立ち上げに関わったひとつです。昔からまちに眠る可能性を見抜き、仲間と形にし、関わった人を次の担い手に変えていく。その循環を生み出す横井さんは、まさに唯一無二のまちのエンジンです。
推薦者4:田中 碧(福井県)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
女子高生のまちづくり参画や子どもの食堂ネットワークづくりなど、市民の挑戦を支える名脇役。
推薦文
「JK課プロジェクト」は、地元の女子高生が“ゆるく”まちづくりに関わる、前例のない挑戦でした。その名称のインパクトもあり、「女子高生を利用するなんて」「常識外れだ」といった批判も受け、市にとってはリスクの高い取り組みでもありました。このプロジェクトを陰で支えたのが、鯖江市職員の横井氏です。
結果として、延べ100人以上の女子高生が参加し、地元への関心や定着にもつながりました。実は私もその一人として参加していた元女子高生です。
バッシングの際、横井氏は「さあ、どうしようか。」と私たちに問いかけ、判断と行動を委ねました。行政が矢面に立つのではなく、主役である市民が考え、動く。その姿勢こそ、「JK課」が大切にしていた価値でした。
横井氏の関わり方は「関わりすぎず、与えすぎず、寄り添う」もので、そのスタンスは他のプロジェクトにも現れています。たとえば、地元の祭りとハンドメイドマーケットを融合させたイベントの大規模化、丹南こども食堂ネットワークの創設、eスポーツを活用した不登校支援などは、多くの市民が主役となり動き出すきっかけになりました。
必要以上に手を出さず、しかし見放すこともなく、そっと見守る。その絶妙な距離感は、多くの人の信頼を寄せ、巻き込んでいく力でした。
行政とは、何かを“してあげる”のではなく、市民の“したいこと”や“困りごと”に耳を傾け、土壌を整える存在。横井氏は、言動で示していました。
現在、公務員となった私自身も、その姿勢から大きな影響を受けています。まちを動かすのは特別な誰かではなく、私たち一人ひとり。そう気づかせてくれた横井氏に、感謝と敬意を込めて、ここに推薦します。
推薦者5:山岸 みつる(福井県)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
自分の業務範疇かどうかに関わらず、分野を問わず、市民が輝く場を傍らで創っていく現場行動派の公務員
推薦文
「なんでそんなところに横井さん!?」
横井さんのすごいところは、私の中ではこの一言にすべて集約されています。そもそも横井さんの鯖江市役所での業務は土木職ですが、それを知ったのは知り合ってから数年経ってからのこと。つまり、土木職であることが意識されないくらい他の色んな場面、キラキラ活躍する市民の傍らにはなぜか横井さんがいて、その市民たちが皆口を揃えて「横井さんが色々動いてくれたんやって~」「横井くんに繋いでもらったんや~」(※福井弁)と言うのです。
市民の一人でもある私自身も例に漏れず、「横井さんのおかげで…」を実体験してきています。例えば私が独立起業する瞬間には、活動拠点とするための空き家候補の紹介、家主との契約がスムーズにいくように間に入って幾度となくコミュニケーションをとってもらい、家主さん側も「横井くんの紹介だから…」ということで私にとってもありがたい条件で契約が決定、それによりその後その拠点には東京の有名企業もサテライトオフィスとして入ってもらったり、その企業が市と連携協定を結んだりと、市の活性化に大きく寄与していくこと事業になりました。表の情報には出てきませんが、これらにおいて傍らで本業関係なく動いてくれたのは横井さんなのです。
他にも、横井さんも運営の中心に関わっていた鯖江のまちづくり一般社団法人「ゆるパブリック」という団体では、私が独立後に最初どう動いていくべきか定まっていないときに「とにかく一度おいで」と声をかけてもらいそこの方々と繋げてもらい、それがその後の事業拡大、そして「地盤・看板・鞄」が何も無い中でまちへの志一本で政界進出を果たす大きな基礎となりました。
横井さんは「なぜそこに」いるのか不明な目撃談の多い公務員です。だからこそ、枠を超えた市民と行政の糸を繋いでまちに変化を起こしていける人。心から横井さんを地方公務員アワードへ推薦いたします。
推薦者6:竹内 陽一(鯖江市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
「市民主役のまちさばえ」のファーストペンギン!若者の「居場所と出番づくり」を続ける令和の必殺仕掛人!
推薦文
横井直人さんは、鯖江市役所の土木技師としての本業に加え、地域の未来を担う若者たちの「居場所と出番づくり」を実現する数々のプロジェクトを立ち上げてきました。今や、福井県下ではスタンダードとなった「地域に飛び出す公務員」のファーストペンギン的な立場で知られており、若者や市民のプロジェクトに伴走しながら、まちづくりの魅力や楽しさを一緒に作り出そうとするその活動が後進の若手職員を触発し、今なお自身はトップランナーとして走り続けています。
特筆すべきは、2014年の発足当時、まちづくりに一番遠い存在として考えられていた女子高校生と地域をつなぐ「鯖江市役所JK課プロジェクト」の創設ですが、それ以前にも、開催が途絶えていた市の花火大会を「さばえ秋HANABI(2011年~)」の実行委員として関わり、地域の人々の想いを花火に乗せて届けるという独自のスタイルで復活。名物「打ち上げメッセージ」は、親から子への感謝やプロポーズ、故人への想いなど、毎年多くの心温まるメッセージが寄せられ、約7,000人が来場する感動的なイベントに成長。また、市民が焼き鳥を囲んで交流するユニークなイベント「焼き鳥合衆国(2013年~)」は、地域の食文化と人のつながりをテーマに、10回にわたり開催。毎回ステージ企画や市民参加型のコンテンツを充実させ、来場者数は数千人規模に達する人気イベントへと成長しました。
横井さんのすごさは、単なるイベント企画にとどまらず、どの所属先でも若者や市民の声を政策に反映させる仕組みを構築するだけでなく、クラウドファンディングや企業協賛を活用し、市民主体の運営体制を築き上げたことで、持続可能な形で地域に根付かせている点にあります。公務員としての枠を超え、地域の未来を見据えた活動を自ら立ち上げ、実行し、育ててきたその姿勢は、まさに「よ!必殺仕掛人!」の一言です。
推薦者7:橋本 健史(越前市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
公務外で次々と展開される幅広い地域活動。その行動力と実践力にはいつも驚かされます。
推薦文
横井さんとは、NPO法人丹南市民自治研究センターという、自治研活動やまちづくり活動を行っている団体で共に活動する仲間です。横井さんは、社会貢献や地域振興など、これまでに数多くの活動実績を残しており、すでに全国的な知名度を持っているような人です。
横井さんを「すごい」と思うところは、土木技師でありながら、直接公務と結びつかないような幅広い活動を次々と生み出す、その行動力と実践力であり、「また新しいことを始めている!」と私たちはいつも驚かされている。
加えて、そこから築かれているであろう人脈も、世間の誰もが知る著名人から地場産業や農業で活躍する市民の方など非常に広い。NPO法人の活動として「プラス+ポケットセミナー(若者、移住者、自治体職員、市民活動の皆さんと一緒に、楽しく自由な発想と視点で語りあう企画)」を行っていましたが、いろんな講師を連れてきてくれて、参加者に貴重な機会を提供してくれ、その行動力・実践力を伝播させている。
極めつけは、実の娘が中学2年生から、暮らしている地域で「こども食堂」を主宰しているということ。どうしたら、そんな子供に育つのだろうか。父である横井さんの姿を見てきたからに違いない。少しでも見習いたいと思って、私も刺激を受けている一人です。
審査員のコメント
公務員の枠を越え、市民の挑戦に寄り添いながら社会的仕組みを立ち上げ、育て続ける稀有な人材。どの活動にも「支援者としての絶妙な距離感」と「持続可能性」があり、10年以上にわたる継続実践と人材育成の成果は圧巻です。「自治を耕す公務員」として、まさにロールモデル的存在です。(橋本 一磨)
とどまることを知らない発想力が凄いです!幅広い活躍の裏には、まちへの深い愛と徹底した対話がベースにあると感じました。(小野寺 崇)
市民の声を反映させるだけでなく、市民主体の運営体制を築き、持続可能なカタチで地域に根付かせるということをやりところにスゴさを感じました。(市橋 哲順)
前例やぶりは公務員にとって重要なこと!それを恐れず実践している姿はまさに主人公のようです。(中村 広花)
横井 直人さん、受賞おめでとうございます!
【地方公務員アワード2025 受賞者の推薦文はこちら】
(1)齋藤 久光 (2)和田 真人 (3)鈴木 満明 (4)油谷 百合子
(5)木下 義昭 (6)天野 博之 (7)朝比奈 克至 (8)村田 大地
(9)上田 昌子 (10)沼 泰弘 (11)及川 慎太郎 (12)横井 直人
【ネクストホープ賞(30歳以下)受賞者の推薦文はこちら】
『地方公務員アワード2025』全体発表はコチラ
協賛

NECグループの社会価値創造をICTで実現する中核会社であり、システムの実装に強みがあります。社内のDXにも継続的に取り組み、その経験を活かし、お客様や社会のDX推進に貢献しています。そして、国内トップクラスの10,000人を超えるエンジニアを擁する企業として、社会基盤をICTで支えるとともに、お客様の企業価値向上や社会課題解決に貢献するSI・サービスを全国で提供しています。

「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、企業とメディア、生活者をつなぐインターネットサービス「PR TIMES」を運営し、地方自治体600市区町村を含む10万社超が利用。地域情報を流通させる為の枠組みづくりとして、47都道府県で銀行、メディア、自治体と提携をし、各地域事業者の情報発信を支援しています。(R7年5月時点)

「AlphaDrive Region」では、地域の可能性を信じて、地域の企業や自治体向けに新規事業開発・人材育成・組織活性化などをご支援いたしております。地域ならではの難しい課題解決に日々向き合う方々の仲間として、共に考えながら伴走支援を行なっております。「地域の未来」を一緒に創っていきましょう。
-300x270.png)
自治体と企業の連携を創出する官民連携事業を展開しています。自治体が抱える社会課題解決に向け、両者の間に入り「導き役」として事業の伴走をし、善き前例をともにつくり、持続可能なまちづくりを推進しています。自治体と企業の強みとニーズ、双方の利益を考え、官民連携の計画から実行、伴走までを行います。

自治体業務において、各種実績をもつ元公務員メンバーを中心に、ふるさと納税・シティプロ・広報支援等を実施。課題抽出・戦略立案といったコンサルティング機能だけでなく、業務実施を担う実働部隊も兼ね備え、地域ごとの課題や理想に伴走。会社の詳細はこちら(https://locusbridge.jp/)

公職研は1971年創業の地方自治専門の出版社です。自治体職員や地方自治関連の出版に加え、人材採用や人材育成、試験制度、研修制度など人事に関わる幅広いテーマで、実務に即した支援を通じて自治体の組織力強化をサポートしています。
自治体の採用業務を支援する、募集情報発信サイト「公務comcom」も運営しております。
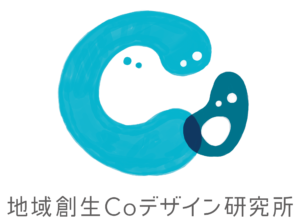
「持続可能な地域を、みんなと一緒に」NTT西日本グループの知見を活かした一気通貫の地域創生コンサルティングにより、「課題探索」から「社会実装」まで伴走する「地域創生」専門の研究所です。まちづくりや観光、GX(グリーントランスフォーメーション)、医療分野などを中心に、地域創生Coデザイン研究所は自治体や企業など地域の主体の皆さまと共に、地域課題の解決をめざしています。
メディア協賛


『自治体通信』は、イシン株式会社が運営する、経営感覚をもって課題解決に取り組む自治体とそれをサポートする民間企業を紹介する情報誌です。全国の都道府県市区町村を中心に合計約30,000部を送付しています。先進自治体の具体的な取り組みをはじめ、自治体経営に役立つ情報をお届けします。

株式会社ジチタイワークスが編集・制作する「ヒントとアイデアを集める行政マガジン」を毎号約11.5万部発行し、WEB版でも限定コンテンツを展開!仕事に活かせる事例を丁寧に取材・紹介し、自治体の課題解決を強力に後押し。また、公私に寄り添う公務員向けセミナーも好評です。

『マイ広報紙』は、毎月1000以上の自治体広報紙を記事ごとにテキストデータ化し公開するプラットフォームです。
自治体毎の情報が1つに詰まった自治体ページや多言語翻訳・音声読み上げ機能、ウェブアクセシビリティ対応など、どなたにも見やすく伝わる広報の実現を目指しています。(運営:スパイラル株式会社)
後援

当センターは活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、地域活性化のための諸活動の支援・地域振興の推進を寄与することを目的に設立し、地域を応援しています。

地域に飛び出す公務員を応援するために、約50人の首長が参加。過去4回にわたって「地域に飛び出す公務員アウォード」を主宰。過去の受賞者プレゼンやサミットの内容はこちら。
![JL-01-Mark-[更新済み]_03](https://www.holg.jp/wp-content/uploads/2019/07/JL-01-Mark-更新済み_03-291x300.png)
Jリーグと全国60のJクラブは地域の人たちをハッピーにしたいと願って、社会連携活動「シャレン!」をおこなってきました。これからもより多くの皆さんと手を取り合って一緒に豊かなまちをつくることに挑戦します。
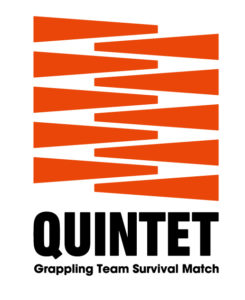
格闘家・桜庭和志が立ち上げた打撃のない安全な組み技競技ブランド。老若男女が取り組める健康増進・防犯対策として、過去に秋田県、生駒市、潟上市と「ねわざ祭」を開催。全国の自治体とも連携を図っています。

Code for Japanは街の課題を市民が主体となってテクノロジーで解決することを目指すシビックテック・コミュニティです。

「社会の無関心を打破する」をミッションに、社会問題に関するスタディツアーを企画運営。地域住民向けにツアー企画スクールを開催し、外部事業者に頼ることのない、持続的な関係人口の創出に貢献しています。詳細はこちら。

マッセOSAKAでは、大阪府内市町村職員に対する研修事業や広域的な行政課題についての調査・研究事業を実施しています。
最新の刊行物、研究成果等詳細についてはこちら。
アンバサダー



