『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2025』、1人目の受賞者の紹介です。
※部署名役職名は推薦文登録時時点のものであり、現在とは異なる場合がございます。
齋藤 久光(四街道市 教育委員会 教育部 社会教育課 図書館 館長)
推薦者1:成瀬 めぐみ(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
図書館の「常識」に風穴をあけ、人とつながる場として再構築した行動力。
推薦文
齋藤さんが四街道市立図書館長に着任してから、現場の空気が少しずつ変わっていくのを、私は日々の仕事のなかで確かに感じてきました。
それは、表向きには目立たないことかもしれません。でも、同じ場所にいる私たちには、確かな手ごたえがありました。
齋藤さんは行政職として図書館に入りました。専門職(司書)である私たちとは、立場も経験も違います。それなのに、いや、それだからこそかもしれませんが、彼の視点はいつも“あたりまえ”を新しく見直すものでした。
たとえば、駅の図書館。通勤通学途中、ふと立ち寄れるような導線を意識して整えることで、「図書館は日常のなかにある」という実感が生まれました。
あるいは、館内に設けたプレーパークやボードゲームの環境づくり。最初は戸惑いもありました。でも、子どもの声や手の動きが混ざる風景は、いつしか私たちの中にも「こういう図書館もあっていい」という新しい感覚を育ててくれました。
なにより印象的だったのは、市民や団体とともに何かを“つくっていく”という姿勢です。これまで地域でつながってきた図書館サポーターと一緒に行う「図書館ん家」には、たくさんのこども連れのママさんが参加されます、中高生がふらっと図書館に立ち寄れる「四街道市立図書館図書部」など、どれも利用者が“自分ごと”として関われるように設計されています。
図書館の事業を、届ける相手の目線から練り上げていく姿勢には、たくさん学ばされてきました。
図書館の可能性を信じながら、既成概念を壊し、人と関係を丁寧に編み直していく。そんな齋藤さんの姿勢と実践は、図書館の新しい在り方を体現していると強く感じています。
推薦者2:関口 笑子(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
「齋藤さん」というだけで「ああ、図書館の」という市民がたくさんいること。
推薦文
齋藤さんが政策推進課にいた頃に地域活動を通じて知り合いました。
みんなが「市役所のさいとうさん」と呼んでいて、さいとうさんに写真を撮ってもらうのを子どもも大人も楽しみにしていたのを思い出します。
さいとうさんの写真はきれいで、オシャレで、とても上手に撮ってくれますが、それ以上にいつも来てくれて、一緒に考えたり、活動してくれるさいとうさんが撮ってくれたことが、それぞれの大切な思い出になっています。
様々な場で写真を目にする機会がありますが、そうした写真を「それ、さいとうさんが撮ってくれて」と紹介されることがあります。
市民活動とか地域活動というとなんだか大きな話に聞こえますが、さいとうさんは写真1枚1枚、撮ってもらった一人一人と市役所をつないできた方です。
「協働ってそういうことだよね」と会うたびに感じています。
今は図書館という会いたいと思ったら行けば会える場にいてくれるので、小さい子たちが「さいとうさんに会えるかな」と図書館を訪れています。
小さい子だけでなく、誰にとってもそういう存在な公務員がいることは四街道の誇るべきポイントです。
齋藤久光さんを推薦します。
推薦者3:和田 浩史(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
どこの部署に異動しても、みんなで地域づくりを実践していること
推薦文
四街道市では、市民協働を「みんなで地域づくり」と定義して、市民の方と行政、その他、そこに関わる人みんなが主体的にいい地域を作ろうという取り組みを行っています。
齋藤氏は、以前、みんなで地域づくりを所管する課の担当者でした。
彼のすごいところは、部署が変わっても、「みんなで地域づくり」の視点がブレないことです。これまで、行政だけで行なってきたような業務でさえ、みんなを巻き込んで、市民と行政で協力してやる仕組みを作ってしまいます。そして、一緒に事業を進めた関係者もとても満足して、充実感を感じているようです。こうして、齋藤マジックにかかった市民のみなさんが、積極的に参加するようになっています。現在在籍している図書館も、学生や高齢者だけでなく、親子が集まる仕組みを作り、様々なイベントを工夫して、すっかり賑やかな楽しい場所に変身しました。
みんなで地域づくりという、ブレない姿勢や、真摯に取り組む姿勢が、関係者に信頼され、齋藤さんがやるならぜひ参加したい、思う市民の方が増えているんだと思います。
推薦者4:岡田 英(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
どの現場でも新しい風を吹き込み、周囲を巻き込み、皆の力を結集して新しいものを創り上げるところです。
推薦文
齋藤さんと初めて仕事で関わったのは、入庁して間もない頃でした。“この人は何か違う”と感じる、そういう存在でした。それは立ち振る舞いや声が大きいとか、わかりやすい違いではなく、むしろ逆で、常に淡々としていて、でも何か“面白いことを起こす気配”を纏っている、そういう人でした。
例えば、部署が変わるたびに、「また齋藤さんが面白いこと始めたらしい」と噂になる。でも、表面だけ見ると派手な取組には見えません。実際は、既にある取り組みの中に少し手を加えて磨き上げたり、目立たない部分に光を当てたり、場の温度や人の動きを見極めながら、じわじわと“流れ”を変えていく。市民や団体、関係者と対話を重ねながら、相手の言葉をすくい上げ、最後には誰もが誇れるような形に仕立てていく。その過程にこそ、齋藤さんのすごみがあると感じています。
ちばコラボ大賞や総務省ふるさとづくり大賞、協働まちづくり表彰グランプリを受賞した「Y(わい)・Y(わい)・NOWSON(のうそん)プロジェクト」では、休耕地を解消しながら、千葉の原風景を守るべく、農村生活と民俗体験ができる“今どきの農村”として整備しました。そこが今は、地域コミュニティの拠点として、「伝統文化・芸術」、「食」、「農」、「学び」を育みながら、外国人も含めた交流人口の増加に繋がるコンテンツとして、ブラッシュアップを重ね、様々な団体や市民の手によって、確かに地域に根付いています。
それは、現在の図書館でも同じで、様々な企画の実施により、図書館が以前よりも市民の“自分の場所”として根付いていると感じます。どんな場所でも前に出すぎず、でも誰よりも深く考え、誰かの「やってみたい」を引き出し、その“一歩”を後押しする。そんな職員がいることが、市民や他の職員にとってどれだけ心強いか。
私はその背中を追いながら、自分の仕事を育てていきたいと思います。
推薦者5:石渡 絵里(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
ありふれた市役所業務を市民の輝く舞台へと変えるスーパー公務員
推薦文
齋藤さんの最大の功績は、当市の市民協働の新しいあり方を開拓し、その可能性を広げてきた点です。まさに、市民と行政が手を取り合う共創の道を切り拓いたパイオニアといえるでしょう。
中でも特筆すべきは、四街道市が誇るみんなで地域づくり事業提案制度の創設とその推進への多大なる貢献です。
平成24年度、齋藤さんは資金を調達し、みんなで地域づくり事業基金を設立。翌年には基金を原資とするみんなで地域づくり事業提案制度(コラボ四街道)をスタートさせました。NPOや自治会など、自主的に地域づくりを行う市民団体が、地域の課題解決や魅力向上に資する事業を市に提案し、市と協力して事業を実施できる画期的な制度です。単なる補助金事業に留まらず、市民団体と市ががっつりタッグを組み、互いの人材や知見、技術などの社会資源を持ち寄り、魅力ある地域づくりを実践していくという四街道市独自のスタイルを築き上げました。
また、「ドラマチック四街道」と銘打たれた様々なコンテンツを通じて、市民参画を強力に推進。市民の想いと写真を日々のオンラインカレンダーにする企画「みんなでカレンダー」や市内在住の色鉛筆画家が街の移り変わりを描く「まちの記憶」など、等身大の四街道を発信しつつも、市民一人ひとりが輝く瞬間にスポットライトをあてた企画力は高く評価され、全国広報コンクール広報企画部門で広報以外の部署では初となる日本広報協会会長賞入選を受賞しています。
市民協働の中核となっている「みんなで地域づくりセンター」の立ち上げにも参画するなど、その功績は書きつくせません。
図書館長となった今も、図書館という概念を取り払い、ボードゲームやプレーパーク、朝飯、お化け屋敷イベントなど度肝を抜かれるようなアイデアを創出し、その土壌に市民を巻き込む力はまさに圧巻です。地域づくりの彼の後任となった立場から自信を持って推薦します。
推薦者6:日比野 龍太(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
広報×市民協働で表彰多数 市民の共感を喚起し、地域を動かすビジョンメーカー
推薦文
私は齋藤さんの後輩として10年以上にわたりそのすごさを間近で見てきました。齋藤さんは複雑な行政情報を市民目線で整理・可視化します。例えば、広報素材においては、単なる告知ではなく、そこに込められた「背景」「狙い」「成果」をストーリーとして紡ぎます。そして、市民の共感を引き出す強力なツールへと昇華させ、市民の当事者感とシビックプライドを同時に醸成することで、次の行動を自然に促します。特に際立っているのは、以下の2つの強みです。
①現場主義と発信力
常に市民の「いま必要な情報」を掘り起こし、言葉・写真・映像を統合したクリエイティビティで、単なる報告にとどまらない「新たな関係性」を構築します。地道な現場改善と緻密な演出企画を高いレベルで両立させるバランス感覚は他に類を見ません。
②多様な世代・団体との協働(市民の担い手化)
一過性で終わらせず、子どもから高齢者、企業、NPO、学校まで、あらゆるステークホルダーを「担い手」として巻き込む仕組みを構築。着任して2年足らずの図書館で「プレーパーク」「朝飯図書館」など、新たなプログラムを次々に立ち上げ、住民参画率を飛躍的に向上させています。
これまで「ちばコラボ大賞」「ふるさとづくり大賞」「協働まちづくり表彰」など多数受賞していることに加え、広報ではなく市民協働の担当として「全国広報コンクール」に5年で4度入賞した先見性と実行力は特筆に値します。シビックプライドや関係人口という概念が定着する前段階で、その可能性に着目し、市民主体のプロモーションを実現した功績はまさに稀有です。
齋藤さんは「市民の、市民による、市民のための行政」を徹底し、信頼を起点とした持続的な地域変革を推進してきました。市民を「共感」から「参画」へ、そして「愛着」へと導くこれまでの信頼関係は、次なる取り組みの実現と深化を支える不動の基盤となっています。
推薦者7:平田 文絵(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
柔軟な発想力と地道な開拓力で、地域と行政・異世代間をつなぐ、縁の下の力持ち!
推薦文
市役所職員でありながら、名カメラマンとしても知られる齋藤さん。
そのすごさは、何といっても“フットワークの軽さ”と、“しがらみや常識を超えて人を支える力”にあります。
齋藤さんは、地域のあらゆるイベントに自ら足を運び、人々の表情や出来事を丁寧に写真に収めてきました。
そのフィルムの中には、地域に生きる人たちの「人生の一瞬」が、あたたかく刻まれています。
特に印象的だったのは、コロナ禍で子どもたちが学校や社会とのつながりを失いかけたときのこと。
母として「何かしたい」と、オンラインでホームルームが出来ないかと動き始めた私に対して、
齋藤さんはすぐに共感し、肩を並べて行動してくれました。
「こうあるべき」「○○せねば」という枠を軽やかに超えて、支えてくれるその姿に、何度も勇気をもらいました。
そんな齋藤さんは、これまでの経験や人脈を活かして、今では図書館の館長として新たな世界に挑戦しています。
ここでもやはり「図書館の常識」を飛び越え、
赤ちゃんや子どもたちがたくさん笑い、お母さんたちもほっと一息つけるような、そんなあたたかな空間を作っています。
学校帰りの子どもたちがふらっと立ち寄れる場所に、そして多世代の交流が自然に生まれる場所に。
図書館をそんな「みんなの居場所」へと変えていく取り組みを、情熱をもって進めています。
「役所の人」という枠を超えて、一人の市民として、一人の人間として人と向き合う——。
齋藤さんは、そんな生き方を体現している人です。
推薦者8:藤田 義昭(鹿沼市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
図書館の市民利活用を促進するための新規事業展開と業務改革
推薦文
ネットで図書館改革の先進的な取り組みを調べていたところ、直感的に参考事例としてぜひお話を伺いたく市議会で視察に訪れました。どこにでもある普通の図書館なのですが、齋藤館長の様々な工夫で努力されていることがわかりました。
具体的には、館内でおしゃべりしてもOKにしたこと、図書館事業としてお茶をしながらの朗読会、夏休み子供の居場所事業など、経費を掛けずにあるものを活かしたり視点を変えたりして新たな価値を生み出していることにとても共感をいたしました。財政不足の状況が多い地方公共団体において、職員の知恵と工夫、やる気次第で地域住民に愛される魅力的な公共施設になることができるという、地味だけれど基本的な施設活用促進の取組であると思います。全く関係のなかった他市からではありますが、齋藤館長を推薦いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。
推薦者9:大越 登美子(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
現在の図書館におけるイベント、図書館でプレーパーク、ボードゲーム、駅の図書館等の事業展開について
推薦文
齋藤久光さんの存在を知ったのは、「齊藤さんがおられる市役所は羨ましい」と市外の方との会話からでした。そして、市の事業の中で、当時も今も変わらず、市民協働について力を入れていますが、その中心的存在であることは、普段、他市の方は知るはずがありません。「こんなふうに寄り添ってくれて」と感謝の声の中に、彼の名前が出てきておりました。
齊藤さんは、その場所にとどまらず、プロモーション、自治振興、そして現在の図書館においても市民にとってのオアシスを醸しだしてくれています。図書館長に就任されてから次から次とでてくるそのアイディアは唯一無二のものです。市民との距離を縮め、現場に出向く姿、イベントの時にもお姿をよく見かけます。異動のたびに「また面白くなるな」と思わせてくれる職員は、そう多くありません。そしてその期待を裏切らず、一つ一つ丁寧に取り上げ、積み重ねてきた努力は、評価されるべきものと思います。きちんと成果として市民に返していく実行力が住民の声に耳を傾け、それは地道な仕事ですが、だからこそ信頼を得るのだと実感しています。
私たち議員は、行政をチェックし、時に提案する立場です。その視点から見ても、齋藤さんのような職員がいることは、まちの未来に希望を持たせてくれ、次の世代へ繋げていけると確信しています。
推薦者10:保坂康平(千葉県)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
図書館の既存概念にこだわらない企画を打ち出し、開かれた図書館をつくっていること。
推薦文
従来、図書館というと、読書・勉強をする場であり、読み聞かせ以外は静かにするのが大切というのが、社会通念だが、齋藤 久光館長就任後は、市内のさまざまな団体とコラボしながら、子供、若者や子育て世代向けのイベントを企画立案し、これまで図書館を身近に感じられなかった層にも開かれた図書館を目指し積極的な活動をしている。
特にアウトドア系のサークルとの団体とのコラボ、生まれたばかりの子供をもった父母や、読書以外の興味をもった小中学生を対象にしたイベントなど、従来の図書館になじみの薄い市民対象のイベントが数多く企画されている。
スマホ、電子図書の普及、読書離れ、興味の多様化などによって、図書館の在り方は、時代とともに大きく変わってきている中、読書・勉強をする場としての図書館は、その存在意義そのものを見直されているといっていいだろう。しかし、前例踏襲が原則の行政を動かすのは並大抵ではない。勇気を出して一歩を踏み出し、新しい図書館のありかたを示し、改革をしようとする齋藤久光館長の発想力、行動力に推薦する。
推薦者11:菊地利恵(四街道市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
どこの部署にいても、どんな立場になっても、「人の可能性を信じ、地域の力に変える人」
推薦文
齋藤さんは、住民協働、自治振興、図書館と部署異動しましたが、立場や所属にとらわれず、常に「人」と向き合い、地域の中の人同士を繋げてきた方です。その関係づくりの根底には、誰もが対等に社会の一員として暮らすべきという、深いまなざしがあります。
その姿勢が象徴的だったのは、障がい者との関わりだと思います。コロナ禍で市の「ふるさとまつり」の実施すら危ぶまれた時期、齋藤さんはイベントの継続ではなく、「この状況だからこそできること」を模索しました。そして生まれたのが、市内の複数の障がい者施設と連携した“障がい者アートによるチャリティTシャツの企画です。
当時、誰もが疲弊し、挑戦をためらう空気の中、齋藤さんは各施設を丁寧に訪ね、障がい者アート作家と語らい、その思いや作品の力に光を当てたのです。Tシャツは多くの市民、または市内で働く人の手に渡り、共通の作品を身につけた人々が町を歩くその光景は、アートの美しさだけでなく、社会のなかで同じ思いを持って共に生きるという心の共鳴を感じさせてくれました。施設にとっては収入や就労の機会の創出にとどまらず、自分たちの表現がまちに受け入れられたという誇りにもつながったはずです。
その後、図書館に異動してからも、障がい者アート作家と力を合わせグッズの制作や、かわいらしい移動書棚の制作など、彼らの活躍の場をさまざまな形で広げています。
私は、齋藤さんに、公務員としてというより住民として深く感謝しています。このまちの空気を、あたたかく、前向きに変えてくれる存在です。彼が手がけてきたものは、間違いなくこの地域の一体感を育ててきました。そんなまちづくりをまっすぐに体現している齋藤さんに私たちは、勇気づけられてきました。
四街道で一緒に働く立場としてこんなに素敵な公務員がいることを、心から誇りに思います。
特別協賛社賞-LOCUS BRiDGE賞

齋藤さんは、広報・シティプロモーション・図書館と、どの部署でも市民の力を信じ続け、向き合い、協働していく精神に感銘を受けました。行政もまちの一員であり、地域の方々、民間事業者と連携しながら、まちにとって何が最善かを考え、実現する姿は公務員のあるべき姿だと考えます。
弊社が掲げるビジョン「人や地域の可能性に夢中になる。」と共通する部分があると感じ、LOCUS BRiDGE賞をお渡しさせていただきます。
特別協賛社賞-ジチタイワークス賞

本を読まなくていい。おしゃべりしてもいい。“静かに本を読む場所”という常識を軽やかに飛び越え、図書館の可能性を広げていく齋藤さん。次々と生まれる面白い仕掛けに、「次は何を?」と期待が高まります。その期待感は、まずは一緒に働く仲間から。やがて、まちの人にも伝播して、多くの人から「齋藤さん、齋藤さん」と慕われる。人とのつながりが希薄になりがちな今、住民とこうした関係性を築けることに心から感動しました。
審査員のコメント
図書館という制度的・物理的枠組みを大胆に再編集し、市民の日常に溶け込む「居場所」へと変容させた実践力は圧巻。制度の設計者・変革者としての視座をもち、多様な担い手との関係性を育て続ける姿勢は、まさにこれからの公共をつくる公務員像です。(橋本 一磨)
様々な部署で動き続け、結果を出し続ける熱意と発想力が凄いです。愛される人柄もとても魅力的!(小野寺 崇)
「みんなで地域づくり」の視点を一貫して持ち続け、住民と一緒に取り組む仕組みをつくり、さらには基金や事業といったカタチに落とし込み、根付かせるところがとてもスゴイ!「一緒に取り組む」ことは、簡単そうに聞こえて、実際は超絶ムズいと思いますが、それをごくごく当たり前のように実践している様子が、推薦文を読んでいて想像できました。(市橋 哲順)
図書館という憩いの場所を交流の場として広げているのはすごい!そんな図書館に行ってみたくなりました。町が大好きという気持ちがつたわってきました。(中村 広花)
図書館はこうあるべきという固定観念にとらわれず挑戦しているところがすごい!しかも、たくさんの人に愛され信頼されているのが推薦文からよく伝わってきました。(安高 昌輝)
齋藤 久光さん、受賞おめでとうございます!
【地方公務員アワード2025 受賞者の推薦文はこちら】
(1)齋藤 久光 (2)和田 真人 (3)鈴木 満明 (4)油谷 百合子
(5)木下 義昭 (6)天野 博之 (7)朝比奈 克至 (8)村田 大地
(9)上田 昌子 (10)沼 泰弘 (11)及川 慎太郎 (12)横井 直人
【ネクストホープ賞(30歳以下)受賞者の推薦文はこちら】
『地方公務員アワード2025』全体発表はコチラ
協賛

NECグループの社会価値創造をICTで実現する中核会社であり、システムの実装に強みがあります。社内のDXにも継続的に取り組み、その経験を活かし、お客様や社会のDX推進に貢献しています。そして、国内トップクラスの10,000人を超えるエンジニアを擁する企業として、社会基盤をICTで支えるとともに、お客様の企業価値向上や社会課題解決に貢献するSI・サービスを全国で提供しています。

「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、企業とメディア、生活者をつなぐインターネットサービス「PR TIMES」を運営し、地方自治体600市区町村を含む10万社超が利用。地域情報を流通させる為の枠組みづくりとして、47都道府県で銀行、メディア、自治体と提携をし、各地域事業者の情報発信を支援しています。(R7年5月時点)

「AlphaDrive Region」では、地域の可能性を信じて、地域の企業や自治体向けに新規事業開発・人材育成・組織活性化などをご支援いたしております。地域ならではの難しい課題解決に日々向き合う方々の仲間として、共に考えながら伴走支援を行なっております。「地域の未来」を一緒に創っていきましょう。
-300x270.png)
自治体と企業の連携を創出する官民連携事業を展開しています。自治体が抱える社会課題解決に向け、両者の間に入り「導き役」として事業の伴走をし、善き前例をともにつくり、持続可能なまちづくりを推進しています。自治体と企業の強みとニーズ、双方の利益を考え、官民連携の計画から実行、伴走までを行います。

自治体業務において、各種実績をもつ元公務員メンバーを中心に、ふるさと納税・シティプロ・広報支援等を実施。課題抽出・戦略立案といったコンサルティング機能だけでなく、業務実施を担う実働部隊も兼ね備え、地域ごとの課題や理想に伴走。会社の詳細はこちら(https://locusbridge.jp/)

公職研は1971年創業の地方自治専門の出版社です。自治体職員や地方自治関連の出版に加え、人材採用や人材育成、試験制度、研修制度など人事に関わる幅広いテーマで、実務に即した支援を通じて自治体の組織力強化をサポートしています。
自治体の採用業務を支援する、募集情報発信サイト「公務comcom」も運営しております。
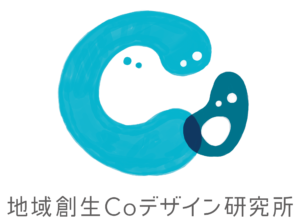
「持続可能な地域を、みんなと一緒に」NTT西日本グループの知見を活かした一気通貫の地域創生コンサルティングにより、「課題探索」から「社会実装」まで伴走する「地域創生」専門の研究所です。まちづくりや観光、GX(グリーントランスフォーメーション)、医療分野などを中心に、地域創生Coデザイン研究所は自治体や企業など地域の主体の皆さまと共に、地域課題の解決をめざしています。
メディア協賛


『自治体通信』は、イシン株式会社が運営する、経営感覚をもって課題解決に取り組む自治体とそれをサポートする民間企業を紹介する情報誌です。全国の都道府県市区町村を中心に合計約30,000部を送付しています。先進自治体の具体的な取り組みをはじめ、自治体経営に役立つ情報をお届けします。

株式会社ジチタイワークスが編集・制作する「ヒントとアイデアを集める行政マガジン」を毎号約11.5万部発行し、WEB版でも限定コンテンツを展開!仕事に活かせる事例を丁寧に取材・紹介し、自治体の課題解決を強力に後押し。また、公私に寄り添う公務員向けセミナーも好評です。

『マイ広報紙』は、毎月1000以上の自治体広報紙を記事ごとにテキストデータ化し公開するプラットフォームです。
自治体毎の情報が1つに詰まった自治体ページや多言語翻訳・音声読み上げ機能、ウェブアクセシビリティ対応など、どなたにも見やすく伝わる広報の実現を目指しています。(運営:スパイラル株式会社)
後援

当センターは活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、地域活性化のための諸活動の支援・地域振興の推進を寄与することを目的に設立し、地域を応援しています。

地域に飛び出す公務員を応援するために、約50人の首長が参加。過去4回にわたって「地域に飛び出す公務員アウォード」を主宰。過去の受賞者プレゼンやサミットの内容はこちら。
![JL-01-Mark-[更新済み]_03](https://www.holg.jp/wp-content/uploads/2019/07/JL-01-Mark-更新済み_03-291x300.png)
Jリーグと全国60のJクラブは地域の人たちをハッピーにしたいと願って、社会連携活動「シャレン!」をおこなってきました。これからもより多くの皆さんと手を取り合って一緒に豊かなまちをつくることに挑戦します。
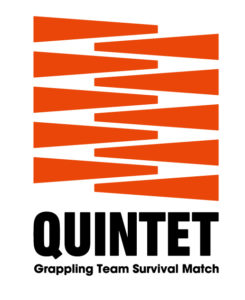
格闘家・桜庭和志が立ち上げた打撃のない安全な組み技競技ブランド。老若男女が取り組める健康増進・防犯対策として、過去に秋田県、生駒市、潟上市と「ねわざ祭」を開催。全国の自治体とも連携を図っています。

Code for Japanは街の課題を市民が主体となってテクノロジーで解決することを目指すシビックテック・コミュニティです。

「社会の無関心を打破する」をミッションに、社会問題に関するスタディツアーを企画運営。地域住民向けにツアー企画スクールを開催し、外部事業者に頼ることのない、持続的な関係人口の創出に貢献しています。詳細はこちら。

マッセOSAKAでは、大阪府内市町村職員に対する研修事業や広域的な行政課題についての調査・研究事業を実施しています。
最新の刊行物、研究成果等詳細についてはこちら。
アンバサダー



