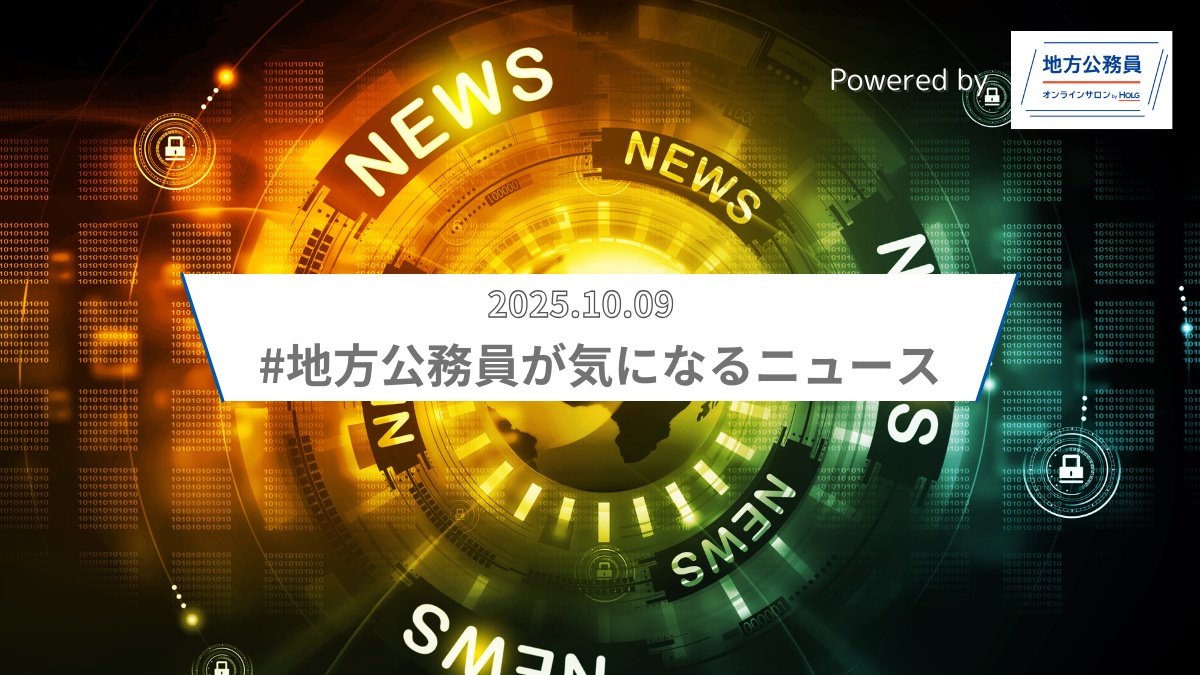記事タイトル:【日経】企業版ふるさと納税が最多 24年度に631億円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA199CR0Z10C25A9000000/
内閣府の発表資料「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の令和6年度寄附実績について(概要)」
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/R06_keinen_zisseki.pdf
(文=晝田 浩一郎)
私自身、内閣府から「企業版ふるさと納税マッチング・アドバイザー」を委嘱していただいたこともあり、企業版ふるさと納税の活用宣伝もかねてです!
内閣府が公表した令和6年度「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」の寄附実績によると、寄附件数は 1万8,457件(前年度比約1.3倍)、寄附額は 631億円超(同約1.3倍)と大幅に拡大しました。制度開始から9年目を迎え、過去最高水準を記録しました。
寄附を行った企業は 8,464社、受け入れた自治体は 1,590団体に達し、全国の半数以上の自治体が制度を活用する段階に入りました。単なる「知る人ぞ知る制度」から「地域政策の有力な財源・協働ツール」へと確実に進化していることがわかりますね!
「地域の産業振興」や「移住・定住促進」など、企業にとっても成果や波及効果がイメージしやすいテーマが大きな寄附を呼び込んでいることが分かります。寄附上位には 横浜市(約410億円)や大阪府(約399億円)など大都市が並びますが、輪島市(約169億円)のように特色ある事業で注目を集めた地方都市も存在します。プロジェクト設計や広報の仕方によって「地方でも大きな成果を得られる」ことを示す好例です。
私個人が好きな考え方や姿勢なのが東川町(北海道)です。自治体としてとても参考になるのでオススメしています。
令和6年度は、寄附金だけでなく「企業が人材を派遣する取組」も116自治体で活用されました。企業のノウハウや専門人材を地域課題の解決に直接つなげる試みは、資金調達にとどまらない協働型地方創生の姿を映し出しています。総務省の「地域活性化起業人」や「ふるさと住民制度」をはじめ、外部人材とも活躍できる場がどんどんと増えてきています。
お金だけではなく、人もモノも企業版ふるさと納税として活用されていっています。
自治体担当者が押さえるべきポイント
今回の実績から以下のポイントがこちら。「営業」の基本的なことを愚直にやるってことが大事です。
1. 事業のストーリー性
寄附が集まるプロジェクトには「地域独自性」「社会的インパクト」「成果の見通し」が明確に描かれています。単なる財源確保ではなく、共感される事業設計がカギです。
2. 企業にとっての価値提示
寄附控除だけでは企業は動きません、言い訳にはなるけど理由にはならないからです。9割控除はどのまちでも同じだからこそ広報協力、実証フィールドの提供、地域課題の共解決やESG経営等への寄与等「リターン」を提示することが重要です。(直接的な利益の供与は禁止)
3. 制度の多面的活用
金銭的な寄附だけでなく、人材派遣や複数分野のプロジェクト設計など、柔軟な活用余地を視野に入れる必要があります。
企業版ふるさと納税は「まちへの寄附」ではなく、「まちへの投資」といった考え方が重要です。金の切れ目が縁の切れ目になるのではなく、官民連携や共創のきっかけとして企業版ふるさと納税を活用ください!!
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます