『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2025』、11人目の受賞者の紹介です。
※部署名役職名は推薦文登録時時点のものであり、現在とは異なる場合がございます。
及川 慎太郎(北見市 総務部 職員課 人材育成担当課長)
推薦者1:城之内 弘宗(名古屋市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
窓口BPRを継続し、窓口BPRと書かないワンストップ窓口を全国に広めた
推薦文
北見市の及川慎太郎さんは、十年以上にわたり市民課業務の本質的な見直しを続け、単なるデジタル化ではなく、「市民も職員も楽になる仕組み」を定着させてきました。その取り組みは一過性に終わらず、若手職員も自然と改善マインドを受け継ぐなど、今や北見市の組織文化となっています。
及川さんの実践は、内閣官房IT総合戦略室が定めた「サービス設計12箇条」にも深く通じるものです。たとえば、「利用者のニーズから出発する」「現場を詳細に観察する」「サービスはシンプルにする」といった原則に沿って、窓口利用体験調査、ワンストップ対応、チェックシート等を地に足のついた形で展開。改善はスモールスタートで始め、定量的に効果(滞在時間)を計測しながら継続してきました。
また、及川さんの取り組みは市内にとどまらず、全国の自治体にBPRのノウハウやツールを無償公開し、現地での支援も精力的に行っています。私自身、前職の三重県桑名市で窓口改革に取り組んだ際、まるで千里眼のように心折れそうなタイミングで声をかけていただき、何度も励まされました。現場や事務局のしんどさを理解しているからこその行動だと思います。
「失敗したことがない。結果が出るまで改善するから」と語る姿勢に、私は地方自治体の未来を変える本物の力を感じ、心から「すごい!」と推薦します。
推薦者2:原田 太(鹿児島市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
北見市の業務改革を主導し、国のアドバイザーとして全国の自治体支援にも取り組んでいるところ
推薦文
及川氏は北見市において業務改革を主導し、顕著な成果を上げた後も、今なお改革を継続している。その豊富な経験を活かし、総務省やデジタル庁の各種アドバイザーとして全国の自治体を支援し、地方公務員のDXやBPRの推進に大きく貢献している。鹿児島市も地域情報化アドバイザーとして及川氏の助言を受け、窓口業務の待ち時間短縮や職員の負担軽減を実現できた。自治体改革の実践者として、及川氏は極めて信頼できる存在である。
推薦者3:川原 祐樹(諫早市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
○業務改革の実践
○DXの体現
○改革実践の支援
・ナレッジの共有
・マインドセット
推薦文
自治体の窓口現場では、長年の慣習が代々引き継がれ、時代とともに住民や職員を取り巻く環境が変化する中、そこに潜む非効率に気づかない、あるいは気づいていても日常業務に忙殺され、前例踏襲に甘んじている場面も多いと思われます。
そのような中、及川氏は窓口業務について、「『業務改革』と『デジタル』の力で、『住民』にも『職員』にも、優しい姿に変えていこう」と呼びかけられています。
及川氏自身、北見市職員として現場からの業務改革に取り組み、全国から注目される「書かないワンストップ窓口」をはじめとする様々な成果を上げるとともに、そのノウハウや資料を惜しみなく公開し、ナレッジの共有にも尽力されています。
これが国や各種メディアからも大きく取り上げられ、なかなか掴みにくかったDXやBPRの具体的なイメージが可視化されたことで、本市を含む多くの自治体が窓口業務改革の第一歩を踏み出す端緒となり、今では全国的なムーブメントになっています。
DXといえば、すぐにデジタルシステムの導入を起想しがちですが、同氏いわく「まずは住民目線、現場目線によるアナログ改革が不可欠であり、そのための手段としてデジタルを組み合わせる」「市民にとってだけでなく、自分たちも楽になるという視点が必要」と説かれます。そのマインドセットが、業務改革の成否を決めると。
本市においても同氏の適確なアドバイスに基づき、現場・行革・デジタルの三位一体の体制を整え、職員による窓口体験調査に始まり、業務フローの見直し、RPA 等による事務の効率化、壁を含む窓口レイアウトやサインの抜本的見直しなどを行い、市民と職員双方よしの窓口改善を進めることができました。
「デジタル」は「業務改革」の手段であり、「業務改革」は「住民と職員の幸福」のための手段であるという、DXの本質を自ら体現し、全国に伝播させているその実践力と影響力がすごい。
推薦者4:前田 泰志(北見市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
窓口業務における本質的な業務改革を主導しモデル的な枠組みを構築。全国各地でノウハウの共有が進む
推薦文
被推薦者は、これまで慣例的に積み上げられてきた自治体窓口業務の改善を推し進めるべく、長きにわたり庁内のワーキンググループや窓口業務改革プロジェクトを主導。日々の業務における気づきなどを具体的に言語化し、課題を顕在化させるとともに、それらに対する解決策をグループワークを通じ職員内から発案させる手法により、改善策の具体化を推し進めた。
本取り組みは、内部的な業務改善のみにとどまらず、いわゆる顧客価値を高めることを主眼におき、カスタマージャーニーを通じて職員自らが窓口手続きを体験することで、利用者の視点での新たな価値の創出を模索させたり、職員が業務を進めやすいよう、内部事務の処理手順の体系化も行ってきた。
また、被推薦者は、デジタルの知見を活かし、業務改革にデジタルツールも活用。地元IT企業と総合窓口受付システムを開発、構築し、今では全国各地の自治体に導入されるようになり、システムの著作権使用料が市の歳入となっている。また、誘致を行った首都圏IT企業との実証実験により、窓口で受付したデータをバックオフィスのシステムへRPAで反映させる仕組みなども実現した。
その結果、従来は各窓口を回る必要があった行政手続きを、書かない・回らない、いわゆる「書かないワンストップ窓口」としての業務モデルを体系化した。
現在も全国各地の自治体から視察が続いており、業務ノウハウの自治体間シェアのモデル的存在となっている。多くの職員や関係者を巻き込み、取り組みを通じて、市民・職員双方がその利益を享受できるモデルとしてその土台を築いた功績はまさに「すごい!」の一言であり、その功績は顕著であるといえる。
推薦者5:時安 洋(山口市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
全国自治体を飛び回り“住民、職員双方良し”の窓口業務改革を支える神様!
推薦文
北見市は窓口業務改革の成功例として全国で最も有名です。その原動力である及川課長は、10年以上にわたって情熱を注ぎ、なんと地元業者と連携して独自の窓口支援システムを構築するほどで、「窓口BPRの神様」と称賛され全国自治体の市民と職員へ笑顔を広めています。
山口市も、新本庁舎整備を契機に「書かない」「待たない」窓口サービスの実現を目指していました。その取り組みへの情熱と覚悟が及川課長の心を打ち、支援につながったのです。他自治体からは「及川さんから学べるなんて、鍛えられますね」。
約3年前、「百聞は一見に如かず」と北見市を視察した際、及川課長は「まずはBPR!その上でデジタル技術を活用し目指す姿を実現。これがDXだ」と、多彩な工夫の紹介と有益なアドバイスをいただき、改革をスタートさせました。
以後、現地及びウェブを通じて指導を受けましたが、及川課長の豊富な経験と知見からのアドバイスにより職員の意識がガラッと変わったんです。当初は不安いっぱいだと漏らしていた25歳以下の若手職員4人が「市民も自分達も楽になるのが面白い」とやる気をみなぎらせ、改革の大きな推進力となりました。この若手職員は改革の経験を生かし続け、未来の山口市を担う人材として成長すると確信しています。
今年5月に新本庁舎で窓口サービスを開始しましたが、市民から「対応が早くなった」「署名だけで済むので便利」との評価が寄せられ、職員からも「無駄が無くなって楽になった」「市民からありがとうと言われるなんて」と大変好評です。
及川課長は今も、全国のどこかの自治体の改革を志す職員の背中を押しています。これは、日本中の市民と職員が業務改革によって笑顔になることを心から願う信念からの活動で、その成果として全国の自治体で窓口業務改革を志す公務員の輪が広がっており、改革の未来が大きく拓けています。私は、凄い公務員だと胸を張って推薦します。
推薦者6:齋藤 理栄(深谷市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
革新的な窓口業務改革を実践「書かないワンストップ窓口」(北見モデル)を全国に拡散している。
推薦文
変革1 人も業務も、とことん変える!
・2011年頃から、住民にも職員にも使いやすい窓口サービスの実現に取り組んできた。全国でお手本にされ私の所属自治体でも2020年から北見市の仕組みを活用
・窓口業務支援システムを北見市と地元ベンダーで共同開発した中心人物。自治体が持つ住民情報を使った自動判定+職員が必要事項を確認しながら手続きを住民と一緒に進めるシステム
・単なるデジタル化ではなく、事務処理手順の見直しやアナログツールの工夫など、現場の声を大切にしながら改善を積み重ねてきた。
・最近は現場から離れた立ち位置から、業務改善や視察対応を通じた現場の人材育成に注力し職員の意識改革やスキル向上を実現
・国からアドバイザーの委嘱を3種類受けている。
変革2 北見市の実践を全国に展開
・実践した窓口業務のノウハウを継続的に発信し続けた結果、全国から視察が殺到中。日経BP視察ランキング2023は5位、2024も10位にランクイン
・システムはデジタル庁のプロジェクトにも採用され、現在60以上の自治体で利用されている。
・業務ノウハウのシェアで北見市と連携している自治体は全国に存在
変革3 北見の人材育成だけじゃなく全国の人材育成にも!
・自治体職員有志での勉強会が、窓口DXを学ぶ輪に広がった。
・第1回デッカイギで「アナログ的視点から始める自治体窓口業務改革」の発表が注目を集める。(2022年1月)
・有志によるオンライン勉強会や、J-LISフェアの会場で窓口改革リアル座談会の企画に参画。業務改善の普及活動はデジタル庁の目に触れ、窓口BPRアドバイザー派遣事業が立ち上がった。(窓口
BPRを学びあい次の自治体へ教える人材を育てる仕組み)
熱量たっぷり変態公務員の親玉
・業務改革を愛しすぎる人
・厳寒の焼肉まつりを口実に全国の情熱職員を北見に呼び寄せ、次世代の変態公務員を生み出している。
推薦者7:布橋 みちる(高岡市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
自治体職員を変える!つなげる! 職員数減少・業務負担増加に苦しむ自治体の救世主!
推薦文
今、窓口業務改革が大きなブームになっています。
なぜなら、自治体の窓口現場が大きく破綻しているから。
やってもやっても終わらない。帰れない。
クレームを受け続け、心の傷がどんどん深くなる。
それが毎日延々と続く。
来庁者にも同僚にも優しくなれず、みんな自分を守ることで精一杯。
マイナンバー制度が始まった10年前から、窓口業務は「安定した業務」ではなくなり、常に揺れ動く「不安定な業務」に変わりました。人口減少に伴い、政策はどんどん細かくなり、1年に何度も事務が追加され、業務量が増しています。一方、組織内ではいまだに「ルーチン業務」と思われ、認識のギャップが生じています。
このような悲惨な窓口現場に一筋の光を当てたのが、北海道北見市。
平成21年から窓口業務改革に取り組み、現在も進化し続けるレジェンドです。事務の根拠の確認とともに、住民の視点で最も効率よく業務をこなせる手法を追求し、窓口そのものや業務のあり方、職員の考え方自体を変える取り組みです。
そして、この北見市のプロジェクトを率いてきたのが及川氏。自らをアップデートし続け、今このときも全国の困っている自治体を助けるため、プライベートの時間を投げうって東奔西走しています。
また、各種セミナーや他自治体へ若手職員を派遣し、自組織の人材育成とともに多くの自治体職員をつなげ、変わる・変えるための大きな推進力となっています。
ただ北見市を真似するだけではなく、各自治体の職員自身が自走できるよう自分たちの「ありたい姿」を描くための後押しをし、氏に関わった多くの自治体が、市民サービスの向上と同時に職員の事務負担の軽減を実現しています。
物事の本質を貫き、変わらないことは絶望、変えることは希望であることを教えてくれる及川氏。苦境に喘ぐ自治体を救う、まさに現代の最強公務員です。
推薦者8:中村 美紀(浜松市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
全国各地の窓口を、徹底した業務改革とデジタルの力で住民も職員もハッピーな窓口に変えていく共創の魔術師
推薦文
北海道北見市職員・及川さんは、「市民にも職員にもハッピーな窓口」を目指し、内部事務の見直しや業務導線の最適化といった地味な改善から、「書かないワンストップ窓口」という先進的な仕組みを構築し、デジタルの力で市民の利便性と職員の負担軽減の両立を実現されました。この取り組みは広く注目され、全国から自治体職員が北見市へ視察に訪れています。及川さんは窓口改革の始め方や進め方などいろいろな手順をまとめて実践知を惜しみなく共有し、他の自治体の改革を力強く後押ししています。
総務省の情報化アドバイザーとしても全国の自治体に取り組み方をアドバイスされており、その影響力は非常に大きなものです。本市も北見市を訪問し、及川さんから直接説明をいただきました。「窓口改革のキモは、業務を軽くし、誰もがわかりやすく簡単にすること」という言葉が印象的でした。華やかなデジタル化の裏にある地道な業務フローの見直しや合意形成こそが改革のカギであると、実体験に基づき教えてくださいました。当時窓口部門を指揮していた私にとっては、とても新鮮かつ刺激的で、窓口改革に後ろ向きだった自分が恥ずかしくなるくらい響きました。実際、人口79万人の本市でも及川さんのアドバイスを大事に、小さな改善から取り組んで、窓口の受付応対や事務処理手順を全部見直して、現場の職員でたくさん研修を重ねた結果、属人的なスキルが求められ悩んでいた30年の歴史ある総合窓口が、職員から見ても処理が速くてラクな窓口へと生まれ変わりました。今年の春の引越し繁忙期では、膨大な件数も、ほぼ18時には受付後の事務処理まで終了できていました。今後、職員数の減少が進む中で、限られた人員でも行政サービスの質を維持するためには、及川さんのような実践者の知見が不可欠です。自治体運営の未来を切り拓く人材として、公務員アワードにふさわしい方であると確信し、力強く推薦いたします。
推薦者9:安田 健二(滝川市)
取り組み概要、「すごい!」と思うポイント
”書かない窓口”を生み出し、全国自治体に広めている
推薦文
市民目線で窓口職場を見つめ直し、法律的な解釈も交えながら、現場職員を動かしトライアンドエラーを繰り返し、書かないワンストップ窓口という北見市のスタイルを確立した。
内部改革に留まらずに、全国の自治体への波及も行っている。他自治体へ乗り込み、講演を行い、窓口体験調査を仕掛けて、全国の自治体での窓口改革ムーブメントにまで仕立て上げている。常人では無い。
特別協賛社賞-自治体通信賞

「書かない窓口と言えば北見市」。日頃様々な自治体の先進事例を拝見する中で、ひと際目立った様子をかねてより目にしておりました。 住民ニーズが多様化する昨今、負担増が計り知れない窓口業務にメスを入れた及川様の功績に感銘を受けました。 窓口改革に加え、及川様が体現するDXの本質の捉え方は、まさに全国レベルで「持続可能な行政運営」の実現に貢献されています。 その影響度の高さを評し、自治体通信賞を授与いたします。
審査員のコメント
DXはアナログから、デジタルは業務改革の手段であり、業務改革は住民と職員の幸福のためという信念を長年に渡り全国に広げ続ける実践力と行動力に脱帽!(海老澤 功)
窓口業務の常識を打ち破り、改革を全国に広げた影響力が圧巻。改善を文化として根付かせ、かつ市民にも職員にも優しいDXを体現する姿は「自治体BPRの理想形」。制度や立場に縛られず、現場に根差した“伝播力ある実践”を称賛したい。(橋本 一磨)
「書かないワンストップ窓口」など様々な技術やノウハウを多くの自治体に対して支援し、貢献している点が凄い!(小野寺 崇)
某ドラマの女医のよう(笑)その自信は周りの安心につながります。自信には努力がつきもの。業務改革はまちづくりの一つです(中村 広花)
市民の満足度を高め、職員にとっても楽になる仕組みを構築。全国自治体の窓口業務に影響を与えた功績は絶大。システムの著作権使用料が市の歳入になっているというのも素晴らしい。本当に「すごい」と思います。(安高 昌輝)
及川 慎太郎さん、受賞おめでとうございます!
【地方公務員アワード2025 受賞者の推薦文はこちら】
(1)齋藤 久光 (2)和田 真人 (3)鈴木 満明 (4)油谷 百合子
(5)木下 義昭 (6)天野 博之 (7)朝比奈 克至 (8)村田 大地
(9)上田 昌子 (10)沼 泰弘 (11)及川 慎太郎 (12)横井 直人
【ネクストホープ賞(30歳以下)受賞者の推薦文はこちら】
『地方公務員アワード2025』全体発表はコチラ
協賛

NECグループの社会価値創造をICTで実現する中核会社であり、システムの実装に強みがあります。社内のDXにも継続的に取り組み、その経験を活かし、お客様や社会のDX推進に貢献しています。そして、国内トップクラスの10,000人を超えるエンジニアを擁する企業として、社会基盤をICTで支えるとともに、お客様の企業価値向上や社会課題解決に貢献するSI・サービスを全国で提供しています。

「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、企業とメディア、生活者をつなぐインターネットサービス「PR TIMES」を運営し、地方自治体600市区町村を含む10万社超が利用。地域情報を流通させる為の枠組みづくりとして、47都道府県で銀行、メディア、自治体と提携をし、各地域事業者の情報発信を支援しています。(R7年5月時点)

「AlphaDrive Region」では、地域の可能性を信じて、地域の企業や自治体向けに新規事業開発・人材育成・組織活性化などをご支援いたしております。地域ならではの難しい課題解決に日々向き合う方々の仲間として、共に考えながら伴走支援を行なっております。「地域の未来」を一緒に創っていきましょう。
-300x270.png)
自治体と企業の連携を創出する官民連携事業を展開しています。自治体が抱える社会課題解決に向け、両者の間に入り「導き役」として事業の伴走をし、善き前例をともにつくり、持続可能なまちづくりを推進しています。自治体と企業の強みとニーズ、双方の利益を考え、官民連携の計画から実行、伴走までを行います。

自治体業務において、各種実績をもつ元公務員メンバーを中心に、ふるさと納税・シティプロ・広報支援等を実施。課題抽出・戦略立案といったコンサルティング機能だけでなく、業務実施を担う実働部隊も兼ね備え、地域ごとの課題や理想に伴走。会社の詳細はこちら(https://locusbridge.jp/)

公職研は1971年創業の地方自治専門の出版社です。自治体職員や地方自治関連の出版に加え、人材採用や人材育成、試験制度、研修制度など人事に関わる幅広いテーマで、実務に即した支援を通じて自治体の組織力強化をサポートしています。
自治体の採用業務を支援する、募集情報発信サイト「公務comcom」も運営しております。
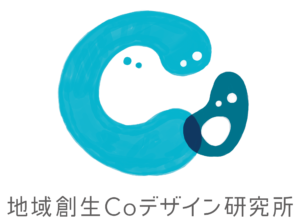
「持続可能な地域を、みんなと一緒に」NTT西日本グループの知見を活かした一気通貫の地域創生コンサルティングにより、「課題探索」から「社会実装」まで伴走する「地域創生」専門の研究所です。まちづくりや観光、GX(グリーントランスフォーメーション)、医療分野などを中心に、地域創生Coデザイン研究所は自治体や企業など地域の主体の皆さまと共に、地域課題の解決をめざしています。
メディア協賛


『自治体通信』は、イシン株式会社が運営する、経営感覚をもって課題解決に取り組む自治体とそれをサポートする民間企業を紹介する情報誌です。全国の都道府県市区町村を中心に合計約30,000部を送付しています。先進自治体の具体的な取り組みをはじめ、自治体経営に役立つ情報をお届けします。

株式会社ジチタイワークスが編集・制作する「ヒントとアイデアを集める行政マガジン」を毎号約11.5万部発行し、WEB版でも限定コンテンツを展開!仕事に活かせる事例を丁寧に取材・紹介し、自治体の課題解決を強力に後押し。また、公私に寄り添う公務員向けセミナーも好評です。

『マイ広報紙』は、毎月1000以上の自治体広報紙を記事ごとにテキストデータ化し公開するプラットフォームです。
自治体毎の情報が1つに詰まった自治体ページや多言語翻訳・音声読み上げ機能、ウェブアクセシビリティ対応など、どなたにも見やすく伝わる広報の実現を目指しています。(運営:スパイラル株式会社)
後援

当センターは活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、地域活性化のための諸活動の支援・地域振興の推進を寄与することを目的に設立し、地域を応援しています。

地域に飛び出す公務員を応援するために、約50人の首長が参加。過去4回にわたって「地域に飛び出す公務員アウォード」を主宰。過去の受賞者プレゼンやサミットの内容はこちら。
![JL-01-Mark-[更新済み]_03](https://www.holg.jp/wp-content/uploads/2019/07/JL-01-Mark-更新済み_03-291x300.png)
Jリーグと全国60のJクラブは地域の人たちをハッピーにしたいと願って、社会連携活動「シャレン!」をおこなってきました。これからもより多くの皆さんと手を取り合って一緒に豊かなまちをつくることに挑戦します。
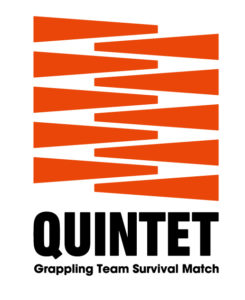
格闘家・桜庭和志が立ち上げた打撃のない安全な組み技競技ブランド。老若男女が取り組める健康増進・防犯対策として、過去に秋田県、生駒市、潟上市と「ねわざ祭」を開催。全国の自治体とも連携を図っています。

Code for Japanは街の課題を市民が主体となってテクノロジーで解決することを目指すシビックテック・コミュニティです。

「社会の無関心を打破する」をミッションに、社会問題に関するスタディツアーを企画運営。地域住民向けにツアー企画スクールを開催し、外部事業者に頼ることのない、持続的な関係人口の創出に貢献しています。詳細はこちら。

マッセOSAKAでは、大阪府内市町村職員に対する研修事業や広域的な行政課題についての調査・研究事業を実施しています。
最新の刊行物、研究成果等詳細についてはこちら。
アンバサダー



